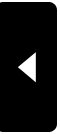2012年11月13日
かたあしだちょうのエルフ
手渡していただいたその絵本を裏返して開くと、そこには図書貸出カードが。
やはり、ありました。
あったのです。
あったのです。
小三・・・。
これは小学校三年生の僕が書いた下手くそな文字。
まだ名字を漢字で書けなかったのですね。
これは小学校三年生の僕が書いた下手くそな文字。
まだ名字を漢字で書けなかったのですね。
僕が通った小学校は10年以上前に廃校になったのですが、幸い異なった用途にて使って下さるNPO法人の方々が現れ、その設備はいまもちゃんと活用されています。
されています、と書きましたが、つい先日までは人づてにそう聞いていただけで実際に見たことはありませんでした。
この日は学校の近くで用事があり、用事が終わった僕は何気なく学校の前で車を停めてみました。
思い出がつまった小学校の前を素通りできなくなったのです。
よく見ると、校庭で畑仕事らしきことをしている方々が数人。
僕は車を降りました。
現在の様子については父母から簡単に説明を受けていましたから、少し近づいてその様子を見てみようと思ったのです。
この日校庭で作業をしていたのは知的障害を持つ方々でした。
されています、と書きましたが、つい先日までは人づてにそう聞いていただけで実際に見たことはありませんでした。
この日は学校の近くで用事があり、用事が終わった僕は何気なく学校の前で車を停めてみました。
思い出がつまった小学校の前を素通りできなくなったのです。
よく見ると、校庭で畑仕事らしきことをしている方々が数人。
僕は車を降りました。
現在の様子については父母から簡単に説明を受けていましたから、少し近づいてその様子を見てみようと思ったのです。
この日校庭で作業をしていたのは知的障害を持つ方々でした。
前述のNPO法人の方々は、この廃校を利用して知的障害者のみなさんのお世話をしていらっしゃるのです。
ぼーっと見ている僕に、一緒に作業をしていたNPO法人のスタッフの方が声をかけてくださいました。
地元出身であること、この小学校の卒業生であること、その他諸々をお話したら、「どうぞ中をご覧ください」とおっしゃってくださいました。
「えっ、良いのですか」と言いながらも、僕は言われるままに玄関でスリッパに履き替えました。
「ああ、この建物は・・・ここは僕が通った小学校に間違いない。」
僕は感慨にふけりました。
「この教室で僕らは学んだのだ・・・。」
職員室、給食室、理科室、音楽室、体育館にプール。
スタッフの方のご厚意で、校内のほとんどすべてを見せていただけたのです。
図書館はとりわけ思い出深い場所でした。
小学校低学年の頃、僕はここでよく本を読んでいたのです。
本は廃校になった当時のまま、棚に置かれていました。
「エルフ・・・エルフ」
僕は心の中でつぶやきました。
懐かしい図書館に入った瞬間、僕が最も愛読した本のことが思い出されました。
本の名前を告げると、スタッフの方は迷うことなく
「ああ、その本なら確かこのあたりに・・・」
歩を進めて棚の前に立ち、一冊の絵本を取り出して僕に手渡して下さいました。
ぼーっと見ている僕に、一緒に作業をしていたNPO法人のスタッフの方が声をかけてくださいました。
地元出身であること、この小学校の卒業生であること、その他諸々をお話したら、「どうぞ中をご覧ください」とおっしゃってくださいました。
「えっ、良いのですか」と言いながらも、僕は言われるままに玄関でスリッパに履き替えました。
「ああ、この建物は・・・ここは僕が通った小学校に間違いない。」
僕は感慨にふけりました。
「この教室で僕らは学んだのだ・・・。」
職員室、給食室、理科室、音楽室、体育館にプール。
スタッフの方のご厚意で、校内のほとんどすべてを見せていただけたのです。
図書館はとりわけ思い出深い場所でした。
小学校低学年の頃、僕はここでよく本を読んでいたのです。
本は廃校になった当時のまま、棚に置かれていました。
「エルフ・・・エルフ」
僕は心の中でつぶやきました。
懐かしい図書館に入った瞬間、僕が最も愛読した本のことが思い出されました。
本の名前を告げると、スタッフの方は迷うことなく
「ああ、その本なら確かこのあたりに・・・」
歩を進めて棚の前に立ち、一冊の絵本を取り出して僕に手渡して下さいました。
僕はスタッフの方と様々な話をしました。
そのほとんどは、僕が思い出をどんどん話し、それに対してスタッフの方が今はこうやって使っていますとか、その話は聞いたことがありますなどとあたたかく受け止めてくれる、といったやりとりで、校舎の中を一緒に歩いている間、僕は自身がどんどん癒されてゆくのを感じました。
もう夕方に近い時間でお疲れだったと思うのですが、突然の来訪者である僕を優しく丁寧に迎えてくださったスタッフの方に頭が下がりました。
かたあしだちょうのエルフの話はよくご存じの方が多いと思います。
手渡されたその絵本のページをめくってあらためてそのストーリーを確認してみたら、スタッフの方とエルフを重ねあわせてしまいました。
実にハードな仕事であることは、たった数十分の滞在でもよくわかりました。
身を削って、心を削って、毎日の業務に取り組んでいらっしゃるのです。
この日、僕の心の中でまた新しい何かが芽生えました。
僕は、また遊びにきます、と告げました。
スタッフの方も、また遊びに来てくださいね、とおっしゃってくださいました。
そのほとんどは、僕が思い出をどんどん話し、それに対してスタッフの方が今はこうやって使っていますとか、その話は聞いたことがありますなどとあたたかく受け止めてくれる、といったやりとりで、校舎の中を一緒に歩いている間、僕は自身がどんどん癒されてゆくのを感じました。
もう夕方に近い時間でお疲れだったと思うのですが、突然の来訪者である僕を優しく丁寧に迎えてくださったスタッフの方に頭が下がりました。
かたあしだちょうのエルフの話はよくご存じの方が多いと思います。
手渡されたその絵本のページをめくってあらためてそのストーリーを確認してみたら、スタッフの方とエルフを重ねあわせてしまいました。
実にハードな仕事であることは、たった数十分の滞在でもよくわかりました。
身を削って、心を削って、毎日の業務に取り組んでいらっしゃるのです。
この日、僕の心の中でまた新しい何かが芽生えました。
僕は、また遊びにきます、と告げました。
スタッフの方も、また遊びに来てくださいね、とおっしゃってくださいました。
2012年11月12日
山里センチメンツについて
(実家の近くで撮影。場所は、秘密。)
そもそもこのブログは、Nordic Walking を楽しむ人々が増えることを目的に活動している僕らの活動を記録しようと思って書き始めたものなのですが、気がつけばただただわが家の日々の暮らしぶりなどを綴る日記のような体裁になっております。
そんなブログなのに毎日読んで下さる方々もいらっしゃるようです。どうもありがとうございます。
これからこのブログを読んで下さるみなさまへ。
お渡ししたカードに書かれていた少々長目のURLをめんどうくさがらずに検索欄に入力してくださいまして、どうもありがとうございます。
そして何かのきっかけでたまたまここに訪れてくださった方々も、ありがとうございます。
ようこそ。
さて、以前の記事で僕が温めている山里センチメンツというプロジェクトをご紹介しました。
どんなものかと言うと、山里に関わる人々の中で僕が気になり、かつ気に入った人に対してインタヴューを申し込み、それをブログのようなものに記してアップして読んでいただく、そのブログのようなもののタイトルを山里センチメンツと名付けて呼ぼうと決めていた次第です。
その件で最近ちょっと考えが変わりました。
インタヴュー集をつくることに変わりはないのですが、山里の明日を考える集まりそのものを山里センチメンツ(ミーティング)と呼んでしまうのも何だか良いかな、と思い始めたのです。
(ちなみに山里センチメンツというネーミングについては、何だかあまり強くない球技サークルの名前みたいで我ながら結構気にいっているのです。がんばれベアーズとか、そういう感じの。笑)
ある日あなたのもとに僕から
「○月○日、○時から○○にて山里センチメンツ・ミーティングを開催します。お食事をしながら山里の未来について楽しく語らいたいと思います。ぜひご参加ください。」
というメッセージが届くかもしれません。
そのときはよろしくお願い申し上げます。
ちなみに僕がこれらのコンセプトでイメージしているセンチメンツという言葉の意味合い・ニュアンスは、いわゆるパブリック・オピニオンの一歩手前、もっと荒削りで情緒的なもの。
さっさと体裁を整えてしまおうとするとどうしてもこぼれ落ちてしまうもの。
それ自体はただの願望だったり、愚痴だったり。
でも決して無視することのできない、人々が日々抱いている様々な気持ち。
そうした情感を指して(山里)センチメンツと呼びたいと思っています。
なお、センチメンタルという言葉は日本語英語として馴染みがありますが、感傷的な、というニュアンスを感じられる方が多いと思います。センチメンツという言葉はそれとはちょっと違って、様々な情感、という意味で使うものだと思ってください。
山里センチメンツ=山里の情感=山里に住んでいる人々や関係する人々の情感
そんな風に捉えていただると幸いです。
そもそもこのブログは、Nordic Walking を楽しむ人々が増えることを目的に活動している僕らの活動を記録しようと思って書き始めたものなのですが、気がつけばただただわが家の日々の暮らしぶりなどを綴る日記のような体裁になっております。
そんなブログなのに毎日読んで下さる方々もいらっしゃるようです。どうもありがとうございます。
これからこのブログを読んで下さるみなさまへ。
お渡ししたカードに書かれていた少々長目のURLをめんどうくさがらずに検索欄に入力してくださいまして、どうもありがとうございます。
そして何かのきっかけでたまたまここに訪れてくださった方々も、ありがとうございます。
ようこそ。
さて、以前の記事で僕が温めている山里センチメンツというプロジェクトをご紹介しました。
どんなものかと言うと、山里に関わる人々の中で僕が気になり、かつ気に入った人に対してインタヴューを申し込み、それをブログのようなものに記してアップして読んでいただく、そのブログのようなもののタイトルを山里センチメンツと名付けて呼ぼうと決めていた次第です。
その件で最近ちょっと考えが変わりました。
インタヴュー集をつくることに変わりはないのですが、山里の明日を考える集まりそのものを山里センチメンツ(ミーティング)と呼んでしまうのも何だか良いかな、と思い始めたのです。
(ちなみに山里センチメンツというネーミングについては、何だかあまり強くない球技サークルの名前みたいで我ながら結構気にいっているのです。がんばれベアーズとか、そういう感じの。笑)
ある日あなたのもとに僕から
「○月○日、○時から○○にて山里センチメンツ・ミーティングを開催します。お食事をしながら山里の未来について楽しく語らいたいと思います。ぜひご参加ください。」
というメッセージが届くかもしれません。
そのときはよろしくお願い申し上げます。
ちなみに僕がこれらのコンセプトでイメージしているセンチメンツという言葉の意味合い・ニュアンスは、いわゆるパブリック・オピニオンの一歩手前、もっと荒削りで情緒的なもの。
さっさと体裁を整えてしまおうとするとどうしてもこぼれ落ちてしまうもの。
それ自体はただの願望だったり、愚痴だったり。
でも決して無視することのできない、人々が日々抱いている様々な気持ち。
そうした情感を指して(山里)センチメンツと呼びたいと思っています。
なお、センチメンタルという言葉は日本語英語として馴染みがありますが、感傷的な、というニュアンスを感じられる方が多いと思います。センチメンツという言葉はそれとはちょっと違って、様々な情感、という意味で使うものだと思ってください。
山里センチメンツ=山里の情感=山里に住んでいる人々や関係する人々の情感
そんな風に捉えていただると幸いです。
タグ :山里センチメンツ
2012年11月12日
A.M.I "Suunto Brand Event"
2012年11月12日
香嵐渓はいまこんな感じです。
これらの写真は、先日の土曜日 (11/10) にうちの奥さんが香嵐渓にて撮影したもの。
もう一週間も待てば渓谷全体が色鮮やかに輝くと思われますが、いま行ってもすでに充分楽しめる状態だそうです。
平日にお時間がとれる方はぜひ足を運ばれると良いでしょう。
ライトアップもすでに始まっております。
2012年11月11日
MR.FRIENDLY
人形焼き風ホットケーキ、と書いたら叱られるでしょうか。
形だけでなく、お味もなかなかgood。
形だけでなく、お味もなかなかgood。
2012年11月08日
山芋のむかご御飯
「そんなにありがたい食べ物かね。」
田舎の方はよくそんなことをおっしゃいます。
見慣れ、食べ慣れた方々にとっては、むかごはさして珍しくないとても平凡なものに映るようなのですが、田舎で育ったくせにこういうものにあまり接することがないまま都会で長らく暮らしてしまった僕のような者からすれば、なかなかレアな食べものという印象です。
塩、米、むかご。
ただそれだけなのですが、素朴な味わいがとても素晴らしいのです。
田舎の方はよくそんなことをおっしゃいます。
見慣れ、食べ慣れた方々にとっては、むかごはさして珍しくないとても平凡なものに映るようなのですが、田舎で育ったくせにこういうものにあまり接することがないまま都会で長らく暮らしてしまった僕のような者からすれば、なかなかレアな食べものという印象です。
塩、米、むかご。
ただそれだけなのですが、素朴な味わいがとても素晴らしいのです。
2012年11月07日
ガレット(galette)と クレープ(crêpe)

香嵐渓シンポジウム2012の鼎談に関する記事はどうなったのよ!?
つづきは書かないの!?
そんなことを思われている方もいらっしゃるかもしれませんね。
つづきは書かないの!?
そんなことを思われている方もいらっしゃるかもしれませんね。

すみません。
ちょっと休憩してよいですか。

以前の記事に書いたように、既に下書き済みであとは体裁を整えて記事としてアップするだけ、という状態にしてあるのですけど、鼎談の内容に関連した本を現在数冊読んでおりまして、どうやらそれらを読み終えてから記事を見直した方が良いと僕の中の誰かが言うのです。
(誰かと言えばそれはもちろん他ならぬ僕なのですけどね。)
(誰かと言えばそれはもちろん他ならぬ僕なのですけどね。)

さて、上の写真は名古屋駅の高島屋の上にあるお店でいただいたガレット (galette) と クレープ (crêpe) です。
僕はフランスに行ったことがありませんが、それでも今頃はもうかなり寒いのだろうな、という想像はつきます。
だから、というわけではないのですが、暖かい店内ではなくて扉の外のテラス席にて、寒空の下、吹きすさぶ風の中で食べました。
僕はフランスに行ったことがありませんが、それでも今頃はもうかなり寒いのだろうな、という想像はつきます。
だから、というわけではないのですが、暖かい店内ではなくて扉の外のテラス席にて、寒空の下、吹きすさぶ風の中で食べました。

これまで訪れた国のなかで、イタリア、イギリス、フィンランド、スウェーデン、デンマークへの訪問はいずれも秋から冬でしたが、寒空の下でも外で物を食べたりお茶を飲んだりしている人たちがやけに多いなと感じました。寒さよりも解放感の方を好むのでしょうね。

2012年11月06日
アケビの皮の甘味噌炒め


きっかけは、矢作川の源流を歩く講座でお世話になった北岡先生の奥さま。
秋はアケビをいただくのが何よりも楽しみだとおっしゃるのですが、お馴染みの中身の話ではありません、皮の部分の話なのです。
秋はアケビをいただくのが何よりも楽しみだとおっしゃるのですが、お馴染みの中身の話ではありません、皮の部分の話なのです。

山形県の方々はアケビの皮を食べるということをテレビのヴァラエティ番組で見て知ってはいましたが、身近に毎年嬉々として食べている方がいるとは!
北岡先生の奥さまは、アケビの皮の中に火を通したひき肉等を詰めて油であげて食べると美味しいわよ、とか、要は茄子と同じ扱いよ、炒めれば良いのよ、とおっしゃっていました。
北岡先生の奥さまは、アケビの皮の中に火を通したひき肉等を詰めて油であげて食べると美味しいわよ、とか、要は茄子と同じ扱いよ、炒めれば良いのよ、とおっしゃっていました。

初回からアケビハンバーグは少々荷が重いので、今回はお手軽な味噌炒めを作ることに。
まずは皮を短冊に切り、湯がいたのち水につけてアク抜き。
まずは皮を短冊に切り、湯がいたのち水につけてアク抜き。

一番外の皮を剥くのを忘れたまま短冊に切ってしまったことに気づき、後で皮をとることに。(不格好なのはそのせいだけではありませんが。)

冷蔵庫を開けたら、しめじと豚肉があったので、アケビと一緒に炒めることにしました。

フライパンに投じてすぐ、ああ、これは食べられる、そう思いました。


だってこんな感じなのです。
ただ油をひいたフライパンの上で火を通しているだけなのですが、既にこの段階でなかなか美味しそうです。
茄子の味噌炒めを作る要領で炒めましたが、お味噌だけは茄子のときよりも甘めにしてみました。
なぜなら、アケビがほろ苦い大人の味だから。
このほろ苦さがたまらない、とアケビの皮好きの方々は口を揃えて言うのです。
ただ油をひいたフライパンの上で火を通しているだけなのですが、既にこの段階でなかなか美味しそうです。
茄子の味噌炒めを作る要領で炒めましたが、お味噌だけは茄子のときよりも甘めにしてみました。
なぜなら、アケビがほろ苦い大人の味だから。
このほろ苦さがたまらない、とアケビの皮好きの方々は口を揃えて言うのです。

とても美味。
機会があればぜひお試しあれ。
機会があればぜひお試しあれ。
タグ :アケビの皮の甘味噌炒め
2012年11月05日
豚の角煮もどうぞ
遠くに住む妹から
「美味しい親子丼って、どこのお店?」
とメールが届きました。
(その一言だけではなくて、別の用事のことも書かれていたのですけどね。)
「実家の近くに親子丼が美味しいお店・・・?はて、ブログに書くほど美味しいお店があったかしら?新しくできたのかな?」
前回の記事を見てそう思って気になったに違いありません。
甥っ子、姪っ子とともに彼女も帰省の折に父母や僕らと一緒に行ったことがあるお店なので今頃、ああ、あそこのお店ね、と腑に落ちているはず。
こちらはうちの妹も食べたことがあると思われる一品。

ご夫婦できりもりしているお店なので無理はきかないはずなのに、とても頑張っていらっしゃいます。
しかし、お客様が多い時間帯に予約なしで伺うとどうしても料理が出されるまでに時間がかかることも。
ですから、さっと来てさっと食べてさっと帰る、という場合には向かないかもしれません。
先日の僕は、時間があると言えばあるけれど一人で暖簾をくぐったという状況だったので、頼んでから比較的早めに食べられるだろうと思われた親子丼を注文した次第。
席を予約されたご家族づれが来店したのとほぼ同時になってしまったので、お店の本棚に置いてあった魯山人関係のことが書かれた雑誌を一冊読めましたが、急いでいなかったのでまったく気になりませんでした。
それに、たまたま隣の席に座っていらっしゃった地元のお人柄の良さげな方と知り合うことができたりと、とても有意義な時間を過ごせました。
金を払ったんだから、と上から目線になってしまう人にはまったく向かないお店です。
もしもあなたがここに行かれたら、お料理のお味とともにどうか過ぎゆく時間も一緒に楽しんでください。

2012年11月04日
2012年11月04日
Incognito

深夜に音楽を。
これは20年前に発売されたシングル。
FMラジオでこの曲を聴き、迷わずその日のうちにCDを買い求めました。
この曲のオリジナルはさらに20年ほど遡った1970年代に言わずと知れた Stevie Wonder がリリースしたもの。
あれはあれでもちろん素晴らしいのですが、こちらの Incognite ヴァージョンの温かみがあって幸福感に溢れる雰囲気がとても好きで、当時の僕は何度も何度も繰り返し聴きました。
彼らは次回来日したら見に行きたいなと思うバンドのひとつです。
なかなか画質の良いライヴの動画を見つけましたので、ぜひこちらもどうぞ。
2012年11月02日
A.M.I "Suunto Brand Event"
香嵐渓シンポジウムに関する記事を続けて書いてまいりましたが、ここでちょっと一休み。
こちらの写真は、若宮町のT-FACEにあるA.M.I nextdoor TOYOTA さんにて撮影させていただいたもの。
ちょっとした用事があって伺ったのです。
以前、Suunto というブランドの腕時計についてある記事で触れましたが、僕が持っている Suunto の Vector という時計はこちらで買い求めました。
その際、お相手をして下さったのは、この方。
前回訪れたときも思ったのですが、こちらのスタッフのみなさんはどなたも洗練された接客、接遇をされるなあと感心。
上っ面だけをなぞるような応対は皆無。
人と人が相対してちゃんと楽しく話をする、そういう自然でリラックスした雰囲気作りができる方々です。
そういう素養のある人を集めているのか、接客トレーニングを会社にて積んでいらっしゃるのか・・・。きっと両方なのでしょうね。
ちょっとした用事があって伺ったのです。
以前、Suunto というブランドの腕時計についてある記事で触れましたが、僕が持っている Suunto の Vector という時計はこちらで買い求めました。
その際、お相手をして下さったのは、この方。
前回訪れたときも思ったのですが、こちらのスタッフのみなさんはどなたも洗練された接客、接遇をされるなあと感心。
上っ面だけをなぞるような応対は皆無。
人と人が相対してちゃんと楽しく話をする、そういう自然でリラックスした雰囲気作りができる方々です。
そういう素養のある人を集めているのか、接客トレーニングを会社にて積んでいらっしゃるのか・・・。きっと両方なのでしょうね。
Suunto はフィンランドの時計ブランドです。
三年ほど前の秋にフィンランド、スウェーデン、デンマークの三ヶ国を巡る北欧旅行に行ったことで、僕は北欧に魅了されました。
中でもフィンランドという国は最も気になる国となり、ヘルシンキの街で見かけたノルディックウォーキングを自らも始めて、さらにこうして Nordic Walking Movement (ノルディック ウォーキング ムーヴメント) というサークルを作ったり、奥さんと一緒になってフィンランド製の食器を買い求めたり、フィンランドについて書かれた本を貪り読んだりと、僕の日々の暮らしとフィンランドは切っても切れないものとなりました。
三年ほど前の秋にフィンランド、スウェーデン、デンマークの三ヶ国を巡る北欧旅行に行ったことで、僕は北欧に魅了されました。
中でもフィンランドという国は最も気になる国となり、ヘルシンキの街で見かけたノルディックウォーキングを自らも始めて、さらにこうして Nordic Walking Movement (ノルディック ウォーキング ムーヴメント) というサークルを作ったり、奥さんと一緒になってフィンランド製の食器を買い求めたり、フィンランドについて書かれた本を貪り読んだりと、僕の日々の暮らしとフィンランドは切っても切れないものとなりました。
Suunto の時計も、僕とフィンランドをぎゅつとつなぐもののひとつ。
毎日(酷使気味ではありますが)愛用しております。
毎日(酷使気味ではありますが)愛用しております。
今回、A.M.I nextdoor TOYOTA さんを訪ねたのはSuunto のイヴェントが今月開かれるとご案内いただいたから。

開催場所を知って、えーっ!と声をあげて驚いた僕!
・・・。
まあ細かいことは抜きにして、余計なことは考えず、とにかく僕もこの日は休みをとってイヴェントに参加させていただくことにしました!
参加者のみなさん、A.M.I のみなさん、どうぞよろしくお願いいたします。
このイヴェントについては、こちらをご覧ください。
ちなみに定員になり次第締め切りとのことですが、僕がお店にうかがった時点ではまだエントリー可能な様子でしたよ。
開催日は11月11日(日)です。
このイヴェントに興味がある方は、まずはA.M.I さんにお問い合わせしてみて下さいね。
開催場所を知って、えーっ!と声をあげて驚いた僕!
・・・。
まあ細かいことは抜きにして、余計なことは考えず、とにかく僕もこの日は休みをとってイヴェントに参加させていただくことにしました!
参加者のみなさん、A.M.I のみなさん、どうぞよろしくお願いいたします。
このイヴェントについては、こちらをご覧ください。
ちなみに定員になり次第締め切りとのことですが、僕がお店にうかがった時点ではまだエントリー可能な様子でしたよ。
開催日は11月11日(日)です。
このイヴェントに興味がある方は、まずはA.M.I さんにお問い合わせしてみて下さいね。
2012年11月02日
2012年11月01日
鼎談 (ていだん) の前に #2
上の画像は実家の母がこしらえた、具沢山(ぐだくさん)栗ご飯。
栗、鶏肉の他に、写真では写し切れていませんが数種類のきのことゴボウも入っていました。
栗の上のご飯粒をよけて写すと格好良かったのですが、そんなことをしてると冷めてしまうのでさっさと撮りました。
見栄えの悪さについてはどうかお許しを。
さて、この記事はひとつ前の記事からの、つづき・・・なのですが、バタバタしてまして、なかなか記事作りができず間が空いてしまいました。
リンクしておくだけでは不親切なので、下記にあらためてまとめます。
・日本は(2011年の)3月11日を境に変わった、高度成長の末に震災を経て全部を都会に集中させる社会から分散型社会に舵が切ろうとする人々が現れ始めた
・しかし実はそもそも日本は昔から地域の独立性で生きてきた国だった
・人任せの社会からもう一度自分たちでものを考える社会にすべきだと思う
・地球一個は足りなくなっている、つまりこのままでは70億人が地球一個で生きられなくなる時が訪れてしまう
・生活はつくるものだということがもう一度見直される
・そして中山間地域での生き方がもう一度見直される時代がくると思っている
一年前。
2011年の香嵐渓シンポジウムの基調講演において、共存の森ネットワークの澁澤寿一氏は上記のようなことを語られたのです。
今回の記事は、そのつづきから。
コーディネーターの農協共済総合研究所 川井氏に促され、足助病院長の早川富博先生と澁澤寿一氏が再び壇上に上がり、フロアーからの質疑応答の時間となりました。
地元の高校生からは
・少子高齢化となってきているのを自身も感じている
・もっと若い人たちが活発に暮すことができれば子供が増えていくのかなと思う
というような発言があり、それに対して早川先生からは
・ここ数十年に繰り広げられたような消費社会のままでいくのか、50年前の暮しに戻るのか、50年前と現代の中間みたいなところを目指すのか、若い世代の方が今後どのような生活を目指すのかがポイントになるのでは
とのコメントが。
澁澤氏は
・足助は底を打って上がり始めているのかもしれないと思う
・空家バンクに申込者が殺到したりしている状況があり、若夫婦が都会から何組かやってきている
・年にひと組ぐらいずつ入ってくるだけで数が確実に維持できるし、あるいは上がってくる
・都会からやってくる若者を各集落が温かく抱え込んでいただければ多分順調に足助は伸びてゆくと感じる
・年収700万、1000万を目指しましょうという時代ではないと思う。
と語られ、消費に重きが置かれたこれまでの生活に最早価値観を見いださず、心身ともに豊かに暮らすためにむしろ生活のサイズダウンすることを望む若者が増えているとおっしゃっています。
そして
・豊田の中山間地域は人が今まで出て行った比率がものすごく大きいからその人たちが帰ってくる余力は他のところに比べたら全然違う
・このあたりの若い人たちは旧豊田市内やせいぜい名古屋など、週に一回実家に帰ろうと思えば帰ることが出来る近距離に出ている人が多いため地域とのつながりが確実に残っている。
・都市と中山間地を組み合わせた生活、そういう生き方をチョイスしたいと若い人たちが思えばものすごくチョイスができる魅力的な地域だと思う
と続けられます。
コーディネーターの川井氏が澁澤氏の発言に「目からうろこでした。」と言われ、フロアーにいる聴衆が思い浮かべるイメージがさらに膨らむように
・ある程度の産業が整った町と、農林業を中心とした山間部での第一次産業とのコラボレーションがとりやすい地域なのかもしれない
と補足のコメントをされました。
そして、「ほかにどうですか。何か今のお話を聞いて。」と会場に呼びかけます。
すると、79歳の方がマイクを握って次のようなことを語り始めました。
・昔の生活はつらかった。親父と一緒に山に行き炭を焚き、雨が降っても田植えをする、それも手で。一日中這いつくばっていて腰が痛くてしょうがない。同時にお金もない。百姓と、山仕事と、貧乏が一番嫌いだった。
・その後、石油を利用するようになり、新幹線や車が走る時代になり、百姓をやるにも、移動をするにも文明の恩恵を受けてきたが、それはそれで昔のつらい暮らしぶりのことを思えば意義があると思える。
・決して間違いではなかったと思うが、地球環境の良くない変化だとか、身近なところでは山が荒れて、耕地も荒れてという様子になってきたのを見て、自然に寄りそう暮らしを望む人々が現れるのは、人間が長く生きる間のサイクルとして理解できる。
・早川先生は「会をつくってこれからみんなでやっていく、会員には息子や孫を入れていく」ということをおっしゃっていたが、「田舎に帰ってこいよ」という話があってもなかなか思うようにはいかない現実があるし、どういう風に手をつけて良いのかと思い悩んでいるこの足助が渋澤先生がおっしゃったように本当に良い方向に今後進んでいけるのか、ジリ貧ではないのか、と不安に思う。
・しかし弱気にならずに、力強く生きていかねばならない、とも思っている。
と正直な気持ちを語られました。
(注:開催記録にはこの79歳の方が発したコメントの一字一句がとても正確に記載されているようなのですが、そのままここに載せてしまうとかなり長くなるし、そしてちょっと伝わりにくい部分もあるため、演者の方たちのコメントと同様に僕なりに要約しています。その分、もしかしたら演者に批判的で当りの強い感じのコメントとして伝わってしまうかもしれませんが、実際のコメントは演者の皆さんに対しての気づかいに溢れたものすごく柔らかいニュアンスの語り口であることを記しておきます。)
澁澤氏は
・まさにおっしゃったサイクルで、もう一回どこまで戻れるかを探していくことになり、それは地域ごとの個性になってくると思う
・お婆ちゃんたちに、どこまでだったら戻れるかと聞いたことがある。つらい暮らしを変えてくれた農業機械の話で例えて考えてもらったら、我々は便利さをとっくに通過してしまったことがわかった
・これからは確実に、便利になっていくのではなく、ある不便さを伴う形に世の中全体が、都市だ地方だということに関わらずなっていくが、それをどう喜びに変えられるかというのは、その地域の知恵だと思う
・あの時代に戻れとは思っていないが、行き過ぎてしまったことだけははっきりしている
・一体どこまで戻れるかということを皆さんと考えていくことが大事であり、その中のひとつが医療の問題なのかなと感じる
早川院長は
・ジリ貧ということで言えば、病院を立て直すときに人口推移のシミュレーションをしたところ、いまのままでいったとしても20年後までは大丈夫という試算 (病院経営が可能という試算) がなされた、しかし地域の人口は少しずつ減っていく
・外に出たご子息も定年退職されたら帰ってくればいい、帰ってきたところに楽しい地域を作っておく、じじばばが住むには医療と介護のセーフティネットが必要、セーフティネットにお金をかけすぎてはいけないのでお金をかけずにどういうセーフティネットをつくるのかというのがぼくらが考えること
・お金が入らない病院は消滅してしまうかもしれないが、そうではないという政策・方法をかんがえた場合は予防医学でいくことになる
・これからは、いかに生きるかということはいかに死ぬかということとイコールになる
・死に方にはいろいろあって良いはずで、家で、病院で、施設で、と最後の最後のところでは選択肢がいろいろあるという多様性を社会がある程度担保するのが理想
・健康的に生きる、あまり病まないように生きるための予防的な医療をしていきたい
・この地域で60代以上の方が楽しみをもって元気でいきいきと生きていることが大事、僕らはみなさんが安心していきいきとされるためのセーフティネットで下支えをするつもりである、そしてそれはできるのではないかと思っている
と、それぞれ心強いコメントを返されました。
ここからはさらに数名の方々が登壇されとても有意義なシンポジウムが行われたようなのですが、今年のシンポジウムのこともそろそろアップしなければなりませんので、昨年の開催記録の紹介はこのあたりでいったんおわりたいと思います。
また別途ご紹介する機会もきっと訪れようかと思いますし、もしも記録をすべて読んでみたいと思われた方は僕に直接コンタクトしていただいても構いません。
開催記録のコピーをお貸しいたします。その場合、まずはこのブログの左下にあるプロフィール欄をご覧くださいね。コンタクト先が記してあります。
※現在のところ、三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会のホームページはweb上に存在しません。会長である早川先生や関係者の方々のお許しをいただいて、研究会やシンポジウムのことをこのブログに書いております。
2012年10月23日
鼎談 (ていだん) の前に #1
というタイトルにしましたが、正確には、鼎談についての記事に進む前に・・・


今回のシンポジウムの会場で、2011年のシンポジウムの開催記録が配布されたとひとつ前の記事で触れました。
昨夜あらためてその内容をじっくりと確認してみて、あっ、このまますっとスルーしてしまうのはいけないな、と気づき、鼎談の記事をアップする前に昨年のシンポジウムについての情報をはさみこむことにした次第です。
僕が研究会に参加したのは今年の夏から。
昨年のシンポジウムにも出席していなくて人づてに話を聞くばかりだったのですが、登壇され鼎談をされた先生方やフロアーの皆様が心をこめて熱く語った言葉の数々を漏らさず書きとめられた開催記録を読んでみたことで、とても素晴らしいシンポジウムであったことがわかりました。
昨年は研究会の会長である足助病院長の早川先生とともにNPO法人「共存の森」から澁澤寿一氏、足助商工会から浅井恒和氏、NPO法人 地域の未来・支援センターから萩原善之氏、くくのち学舎から渕上周平氏、農協共済総合研究所から川井真氏が登壇されたとのこと。
記録のすべてをここに書き写してしまいたいぐらい、価値ある議論が交わされているのですが・・・それをしていると今年の鼎談に辿りつくのはクリスマスぐらいになってしまいそうですから、やめておきます。
今年と同じく足助病院の後藤継一郎事務長が開会を宣言するとともに、シンポジウムの総合コーディーネーターとしてお招きした川井真氏を紹介されるところから記録は始まります。
その川井氏が自己紹介の挨拶にて、
・日本中のあらゆる人々が様々な不安を抱えているが、質は違えど実は根本は極めて似通った問題で苦悩し続けている
・それらの問題を解決する手段のひとつとして地域力が求められている
・日本の後を追うように今後急速に高齢化の道を辿るアジアの他の国々は、一足早く正念場を迎えている日本がどう乗り切るかを注視しているのでうまく乗り切れば新しい社会モデルをアジアに示すことになる
・自然から搾取するのではなく自然と共に生きてきた日本人の強みと島国という日本の地理的強みなど地域力を高めやすい要素が揃っている
などの話をされたと書いてあるのですが、客席に座ってシンポジウムに参加している人々に俯瞰の視点を持たせるとともに前向きなイメージを与えられようとしていらっしゃる様子がとてもよく伝わってきました。
その後、川井氏が早川先生を紹介され、早川先生から「三河中山間の地域力を考える」~中山間地域における当院の取り組み~というタイトルで、スライドを用いながらの趣旨説明が始まり、病院と研究会の両方について様々な取り組みの詳細ともに熱い思いを語られています。
特に研究会がやっていること、やろうとしていることついては今後もこのブログ等で紹介していきますのでこの記事では割愛しますがこの記録を読むことで、地域に住む人だけでなく地域外の多くの人々が注目する大胆な行動指針をあらためて胸にしっかりと刻み込むことができました。
基調講演は「日本の里山に生きること」というタイトルにて澁澤寿一氏が、
・日本は(2011年の)3月11日を境に変わった、高度成長の末に震災を経て全部を都会に集中させる社会から分散型社会に舵が切ろうとする人々が現れ始めた
・しかし実はそもそも日本は昔から地域の独立性で生きてきた国だった
・人任せの社会からもう一度自分たちでものを考える社会にすべきだと思う
・地球一個は足りなくなっている、つまりこのままでは70億人が地球一個で生きられなくなる時が訪れてしまう
という問題提起をされたのち、ご自身が秋田の山奥の集落をこの20数年間訪ね続けているというエピソードを紹介されます。その昔、秋田では過去に大規模な飢饉が起きて大勢の人々が命を落としているが、その集落では古文書が残っている過去300年間において一人の餓死者も出していないというのが通い出したきっかけだそうです。ここには書きませんが、その秘密はとても興味深いものでした。
他にも、山形の置賜地方の草木塔や馬頭観音、庚申塚、お不動さんの写真を紹介し、人々が自然といかに共生しようとしてきたかについて語られたり、沖縄のオジイ、オバアが生きる上で大切にしているポリシーのようなものの紹介など、その場でぜひ聴きたかったと思えるエピソードが続きます。
・生活はつくるものだということがもう一度見直される
・そして中山間地域での生き方がもう一度見直される時代がくると思っている
澁澤さんは聴衆に向かってそう語りかけています。
さて。
このあと質疑応答の時間になり、フロアーにマイクが渡るのですが・・・
ここからが面白いのです。
面白いと書いては、当事者の方に叱られるかもしれませんが、たぶん昨年のシンポジウムにおけるとても素晴らしいやりとりのひとつだったのではないかと想像します。
そのことは次の記事で書きますね。
今年の鼎談のこと?
はい、中沢先生の登場は次の次の記事となります。
もう書いてありますから後はここにアップするだけなのですが、その前に2011年のこと、あともう一回だけ書かせてください。
To be continued.
昨夜あらためてその内容をじっくりと確認してみて、あっ、このまますっとスルーしてしまうのはいけないな、と気づき、鼎談の記事をアップする前に昨年のシンポジウムについての情報をはさみこむことにした次第です。
僕が研究会に参加したのは今年の夏から。
昨年のシンポジウムにも出席していなくて人づてに話を聞くばかりだったのですが、登壇され鼎談をされた先生方やフロアーの皆様が心をこめて熱く語った言葉の数々を漏らさず書きとめられた開催記録を読んでみたことで、とても素晴らしいシンポジウムであったことがわかりました。
昨年は研究会の会長である足助病院長の早川先生とともにNPO法人「共存の森」から澁澤寿一氏、足助商工会から浅井恒和氏、NPO法人 地域の未来・支援センターから萩原善之氏、くくのち学舎から渕上周平氏、農協共済総合研究所から川井真氏が登壇されたとのこと。
記録のすべてをここに書き写してしまいたいぐらい、価値ある議論が交わされているのですが・・・それをしていると今年の鼎談に辿りつくのはクリスマスぐらいになってしまいそうですから、やめておきます。
今年と同じく足助病院の後藤継一郎事務長が開会を宣言するとともに、シンポジウムの総合コーディーネーターとしてお招きした川井真氏を紹介されるところから記録は始まります。
その川井氏が自己紹介の挨拶にて、
・日本中のあらゆる人々が様々な不安を抱えているが、質は違えど実は根本は極めて似通った問題で苦悩し続けている
・それらの問題を解決する手段のひとつとして地域力が求められている
・日本の後を追うように今後急速に高齢化の道を辿るアジアの他の国々は、一足早く正念場を迎えている日本がどう乗り切るかを注視しているのでうまく乗り切れば新しい社会モデルをアジアに示すことになる
・自然から搾取するのではなく自然と共に生きてきた日本人の強みと島国という日本の地理的強みなど地域力を高めやすい要素が揃っている
などの話をされたと書いてあるのですが、客席に座ってシンポジウムに参加している人々に俯瞰の視点を持たせるとともに前向きなイメージを与えられようとしていらっしゃる様子がとてもよく伝わってきました。
その後、川井氏が早川先生を紹介され、早川先生から「三河中山間の地域力を考える」~中山間地域における当院の取り組み~というタイトルで、スライドを用いながらの趣旨説明が始まり、病院と研究会の両方について様々な取り組みの詳細ともに熱い思いを語られています。
特に研究会がやっていること、やろうとしていることついては今後もこのブログ等で紹介していきますのでこの記事では割愛しますがこの記録を読むことで、地域に住む人だけでなく地域外の多くの人々が注目する大胆な行動指針をあらためて胸にしっかりと刻み込むことができました。
基調講演は「日本の里山に生きること」というタイトルにて澁澤寿一氏が、
・日本は(2011年の)3月11日を境に変わった、高度成長の末に震災を経て全部を都会に集中させる社会から分散型社会に舵が切ろうとする人々が現れ始めた
・しかし実はそもそも日本は昔から地域の独立性で生きてきた国だった
・人任せの社会からもう一度自分たちでものを考える社会にすべきだと思う
・地球一個は足りなくなっている、つまりこのままでは70億人が地球一個で生きられなくなる時が訪れてしまう
という問題提起をされたのち、ご自身が秋田の山奥の集落をこの20数年間訪ね続けているというエピソードを紹介されます。その昔、秋田では過去に大規模な飢饉が起きて大勢の人々が命を落としているが、その集落では古文書が残っている過去300年間において一人の餓死者も出していないというのが通い出したきっかけだそうです。ここには書きませんが、その秘密はとても興味深いものでした。
他にも、山形の置賜地方の草木塔や馬頭観音、庚申塚、お不動さんの写真を紹介し、人々が自然といかに共生しようとしてきたかについて語られたり、沖縄のオジイ、オバアが生きる上で大切にしているポリシーのようなものの紹介など、その場でぜひ聴きたかったと思えるエピソードが続きます。
・生活はつくるものだということがもう一度見直される
・そして中山間地域での生き方がもう一度見直される時代がくると思っている
澁澤さんは聴衆に向かってそう語りかけています。
さて。
このあと質疑応答の時間になり、フロアーにマイクが渡るのですが・・・
ここからが面白いのです。
面白いと書いては、当事者の方に叱られるかもしれませんが、たぶん昨年のシンポジウムにおけるとても素晴らしいやりとりのひとつだったのではないかと想像します。
そのことは次の記事で書きますね。
今年の鼎談のこと?
はい、中沢先生の登場は次の次の記事となります。
もう書いてありますから後はここにアップするだけなのですが、その前に2011年のこと、あともう一回だけ書かせてください。
To be continued.
2012年10月23日
香嵐渓シンポジウム2012 レポート #2
「皆さんこんにちは。本当に良い天気なので、外で元気に体操した方が良いのですけども・・・健康ネットワーク研究会がこんな良い天気でこんな暗い中でディスカッションをしていて良いのだろうかと・・・。多数お集まりいただきありがとうございます。」
ユーモアに溢れる語り口に、会場からは早速笑いが。
シンポジウムの総合司会である足助病院長 早川富博先生の冒頭挨拶はこんな感じで始まりました。
シンポジウムの総合司会である足助病院長 早川富博先生の冒頭挨拶はこんな感じで始まりました。
以下はそのとき早川先生が述べられたこと。
・シンポジウム(報告会)は今回が第三回。
・毎年やろうと決めている。
・皆さんのお手元にある冊子について。
事務局のスタッフが昨年のシンポジウムを録音したテープを密かに文字に起こしてくれていた。それを知り、一年遅れにはなるが文章にまとめて報告書を作成し配布することに。
報告書の表紙の絵は、名古屋造形大学 "やさしい美術" の面々によるもの。
・シンポジウム(報告会)は今回が第三回。
・毎年やろうと決めている。
・皆さんのお手元にある冊子について。
事務局のスタッフが昨年のシンポジウムを録音したテープを密かに文字に起こしてくれていた。それを知り、一年遅れにはなるが文章にまとめて報告書を作成し配布することに。
報告書の表紙の絵は、名古屋造形大学 "やさしい美術" の面々によるもの。


学生さんたちが足助病院の中で足かけ8年、美術の仕事をしてくれている。絵はひとつの集落を現わしている。かなりの数の原案の中から投票で選ばれたもの。埋もれてしまうのはもったいないのため表紙に用いさせていただいた。
・香嵐渓シンポジウムという名前について。十数年前、当時の足助町により同じ名前のシンポジウムが開かれた。豊田市と合併した現在においても、この地域の心意気を示すための名前として、香嵐渓シンポジウムという名前を用いてゆきたい。
・香嵐渓シンポジウムという名前について。十数年前、当時の足助町により同じ名前のシンポジウムが開かれた。豊田市と合併した現在においても、この地域の心意気を示すための名前として、香嵐渓シンポジウムという名前を用いてゆきたい。
2012年10月22日
香嵐渓シンポジウム2012 レポート #1
素晴らしい秋晴れとなった10月20日の土曜日。
僕らは足助の飯盛座にて開催された香嵐渓シンポジウムの会場に足を運びました。
そのときの様子を記事にしたいと思うのですが、情報量は膨大です。
よって何回かに分けて書くことになります。
どうかご容赦を。
そしてどうぞお楽しみに。
特に、このシンポジウムに興味を持ったが当日参加できなかったという方、このブログにしばしお付き合いいただけたら幸いです。
鼎談についてはメモを元に、要点をまとめたものを記事として記していきますが、先生方の発言内容やそのニュアンスが実際と異なってしまってはいけないので、会場で鼎談を聞かれた方が僕が書いた記事を読んでも首を捻ることのないクオリティーにすべく、出来る限りの努力します。
僕らは足助の飯盛座にて開催された香嵐渓シンポジウムの会場に足を運びました。
そのときの様子を記事にしたいと思うのですが、情報量は膨大です。
よって何回かに分けて書くことになります。
どうかご容赦を。
そしてどうぞお楽しみに。
特に、このシンポジウムに興味を持ったが当日参加できなかったという方、このブログにしばしお付き合いいただけたら幸いです。
鼎談についてはメモを元に、要点をまとめたものを記事として記していきますが、先生方の発言内容やそのニュアンスが実際と異なってしまってはいけないので、会場で鼎談を聞かれた方が僕が書いた記事を読んでも首を捻ることのないクオリティーにすべく、出来る限りの努力します。
さて。
この方の後頭部に見覚えのある方はいらっしゃいますか?
はい。
そうです。
正解。
これは、今回のシンポジウムの総合司会を務められた足助病院院長の早川先生の後姿です。
僕はこういうシンポジウムや講演会等のイヴェントではいつも最前列またはそのすぐ後ろあたりに座るようにしているのですが、この日陣取った席は、何と早川先生の斜め後ろの席だったのです。
さらに開会の直前には中沢先生がどこからともなく (?) 風のように軽やかに現れて、僕の前の席 (つまり早川先生の横の席) に笑顔で腰掛けられました。
目の前には中沢先生の後頭部が。
鼎談が始まるまでのわずかな間だけ先生方がいらっしゃる席とはいえ・・・、自分は何という席に座ってしまったのかと頭を抱えました。
リラックスして談笑する先生方。
その後ろで、緊張している僕・・・。
開会となり先生方が壇上に上がられて、やっと一息ついた次第でした。
この方の後頭部に見覚えのある方はいらっしゃいますか?
はい。
そうです。
正解。
これは、今回のシンポジウムの総合司会を務められた足助病院院長の早川先生の後姿です。
僕はこういうシンポジウムや講演会等のイヴェントではいつも最前列またはそのすぐ後ろあたりに座るようにしているのですが、この日陣取った席は、何と早川先生の斜め後ろの席だったのです。
さらに開会の直前には中沢先生がどこからともなく (?) 風のように軽やかに現れて、僕の前の席 (つまり早川先生の横の席) に笑顔で腰掛けられました。
目の前には中沢先生の後頭部が。
鼎談が始まるまでのわずかな間だけ先生方がいらっしゃる席とはいえ・・・、自分は何という席に座ってしまったのかと頭を抱えました。
リラックスして談笑する先生方。
その後ろで、緊張している僕・・・。
開会となり先生方が壇上に上がられて、やっと一息ついた次第でした。
時計の針を少し戻します。
こちらは開会前の様子。受付をするおじいちゃん、おばあちゃんたち。
地元地域に住んでいらっしゃる大勢の方が、飯盛座にいらっしゃいました。
To be continued.