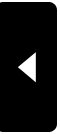2012年12月07日
スティーブ・ジョブズ全発言

この本を読んでから、某政党がのたまう国防軍構想について考えてみると・・・
①軍隊などという時代遅れの組織をこの日本という国においていまさら作る意味はなし。
②もしも自衛隊をリニューアルするならば、世界初の新しい機能を持つ新しい組織として作り直すべき。法律もそれにあわせて新たに作るだけ。
③その世界初の新しい組織は世界に模範を示すもので、他国が簡単に真似できないほどの素晴らしいものにすべき。
④その新しい組織は、世界平和について研究する機関と、国防活動をする機関をひとつにした構造とし、両者の持つ力は組織内で拮抗するものとする。
⑤平和について研究する機関は膨大な研究成果を産み出すのを目的として内外の優秀な人材を集めたものとし、全世界にその膨大な研究成果を知らしめる強い発信力を持ち、そのことにより世界から日本が一目置かれる存在になれるものとする。たとえば、アメリカを銃社会では無くしてしまうほどの影響力を持つ、など。
⑥国防活動をする機関は、他国からの侵略を防ぐための活動の他に、自衛隊以上に国内外の災害対応、人命救助対応に迅速に出動可能で頼りになる存在として国民から尊敬されるものとする。原子力発電所の廃炉作業の一部を担うセクションも持つこととする。
⑦上記のような組織を作ると決意して行動を開始してしまえば、軍事面で今後もしばらくアメリカにフォローされ続ける理由は明快になる。つまりアメリカの軍事力は、日本が上記の組織を作るまでの時限的な盾のようなものと考えておくことができる。
上記を読んで
バカかお前は
と思われた方。
そうかもしれません。
夢のような話。
実現できない話。
逆立ちしたってできっこない到底無理な話なのかもしれません。
でも。
無理だと思われたことでも、時が経って実現したことなんて人類の歴史において沢山あるではありませんか。
真似したり、改良したりするのは得意だけれど、一から新しいものを作ることが苦手なわがくに。
しかし、震災以後を耐えた東北の若者から優れた政治家や研究者が現れるに違いありません。
彼らは、きっと新しいものをつくる。
彼らは、きっと新しいくにをつくると思うのです。
今度の選挙は悩ましいと思われている方。
悩ましいのは当たり前。
次世代のために、良い方向に導く可能性がわずかでもあるところに賭けましょう。
ただそれだけです。
未来のために、広い広い砂漠にある砂粒の中のひとつのような一票を、とにかく行使するだけです。
悪い方向に導く可能性がわずかでもあるところに賭けてはいけません。
特に、次世代の"命"に関わるような重大な問題を作り出してしまう恐れを排除するために、消去法で諸々を選択していくしかないのは明らかです。
全部消えた?
はい、もう一度。
全部消しては駄目です。
無理矢理ひとつを絞り出すのです。
選挙は、いまを劇的に変えられるものではないって、今までの世界の歴史やあなたの人生の中でもう充分学んだではありませんか。
選挙は、あなたがこの世からいなくなってからの世の中の在り様を決定するものと言っても過言ではありません。
僕やあなたはこの後もう何年もこの世にいない。近々、消えてなくなりますが、一票を通して、この世からあなたがいなくなっても世の中に影響力を残せるのです。
残したことになるのです。
それが砂漠の砂粒のひとつ程度の大きさであっても。
選挙に行かないでどうする?
行っても無駄?
無駄かどうかはあなたが生きているうちには絶対わかりませんよ。
行かないことは、人間という動物に産まれた価値を捨てることと等しいです。
東北から、被災地から、若くて優れた、新しいことを次々とやってのける勇気ある政治家たちが次々と誕生するまで、それまでのいましばらくあいだ、あなたや僕が彼らや彼女らを、彼らや彼女らの未来を守ってあげなければいけないのです。
次世代のさらに次世代が、選挙で期待をこめて一票を投じられるような政治家が次世代から誕生するはずです。
そう思ったら、砂粒のほんのひとつであってもぶん投げてみたくはなりませんか?
①軍隊などという時代遅れの組織をこの日本という国においていまさら作る意味はなし。
②もしも自衛隊をリニューアルするならば、世界初の新しい機能を持つ新しい組織として作り直すべき。法律もそれにあわせて新たに作るだけ。
③その世界初の新しい組織は世界に模範を示すもので、他国が簡単に真似できないほどの素晴らしいものにすべき。
④その新しい組織は、世界平和について研究する機関と、国防活動をする機関をひとつにした構造とし、両者の持つ力は組織内で拮抗するものとする。
⑤平和について研究する機関は膨大な研究成果を産み出すのを目的として内外の優秀な人材を集めたものとし、全世界にその膨大な研究成果を知らしめる強い発信力を持ち、そのことにより世界から日本が一目置かれる存在になれるものとする。たとえば、アメリカを銃社会では無くしてしまうほどの影響力を持つ、など。
⑥国防活動をする機関は、他国からの侵略を防ぐための活動の他に、自衛隊以上に国内外の災害対応、人命救助対応に迅速に出動可能で頼りになる存在として国民から尊敬されるものとする。原子力発電所の廃炉作業の一部を担うセクションも持つこととする。
⑦上記のような組織を作ると決意して行動を開始してしまえば、軍事面で今後もしばらくアメリカにフォローされ続ける理由は明快になる。つまりアメリカの軍事力は、日本が上記の組織を作るまでの時限的な盾のようなものと考えておくことができる。
上記を読んで
バカかお前は
と思われた方。
そうかもしれません。
夢のような話。
実現できない話。
逆立ちしたってできっこない到底無理な話なのかもしれません。
でも。
無理だと思われたことでも、時が経って実現したことなんて人類の歴史において沢山あるではありませんか。
真似したり、改良したりするのは得意だけれど、一から新しいものを作ることが苦手なわがくに。
しかし、震災以後を耐えた東北の若者から優れた政治家や研究者が現れるに違いありません。
彼らは、きっと新しいものをつくる。
彼らは、きっと新しいくにをつくると思うのです。
今度の選挙は悩ましいと思われている方。
悩ましいのは当たり前。
次世代のために、良い方向に導く可能性がわずかでもあるところに賭けましょう。
ただそれだけです。
未来のために、広い広い砂漠にある砂粒の中のひとつのような一票を、とにかく行使するだけです。
悪い方向に導く可能性がわずかでもあるところに賭けてはいけません。
特に、次世代の"命"に関わるような重大な問題を作り出してしまう恐れを排除するために、消去法で諸々を選択していくしかないのは明らかです。
全部消えた?
はい、もう一度。
全部消しては駄目です。
無理矢理ひとつを絞り出すのです。
選挙は、いまを劇的に変えられるものではないって、今までの世界の歴史やあなたの人生の中でもう充分学んだではありませんか。
選挙は、あなたがこの世からいなくなってからの世の中の在り様を決定するものと言っても過言ではありません。
僕やあなたはこの後もう何年もこの世にいない。近々、消えてなくなりますが、一票を通して、この世からあなたがいなくなっても世の中に影響力を残せるのです。
残したことになるのです。
それが砂漠の砂粒のひとつ程度の大きさであっても。
選挙に行かないでどうする?
行っても無駄?
無駄かどうかはあなたが生きているうちには絶対わかりませんよ。
行かないことは、人間という動物に産まれた価値を捨てることと等しいです。
東北から、被災地から、若くて優れた、新しいことを次々とやってのける勇気ある政治家たちが次々と誕生するまで、それまでのいましばらくあいだ、あなたや僕が彼らや彼女らを、彼らや彼女らの未来を守ってあげなければいけないのです。
次世代のさらに次世代が、選挙で期待をこめて一票を投じられるような政治家が次世代から誕生するはずです。
そう思ったら、砂粒のほんのひとつであってもぶん投げてみたくはなりませんか?
2012年12月07日
いのちと放射能
僕らがいま読まなければいけない本のうちの、一冊です。

2012年12月07日
2012年12月07日
2012年12月06日
オカリナ重奏グループ おかり~な・フレンズ

このチャーミングな女性たち。
彼女たちが、オカリナ重奏グループ おかり~な・フレンズの面々です。
彼女たちが、オカリナ重奏グループ おかり~な・フレンズの面々です。

オカリナの音色はとてもあたたかい。
今回彼女たちの演奏を聴いて、そう思いました。
あらためて、拍手を送ります。
素敵な音色を聴かせていただきどうもありがとうございます。
野外でアコースティック楽器を上手に演奏しようとすること自体、かなりハイレヴェルな腕前を必要とすると言うのに、今回は初冬の冷え込む山頂での演奏。
気温や湿度など、空間のコンディションに大きく左右されるオカリナという楽器の (素材からもたらされる) 特性上、音程を安定させるのが (それも三人の持つ三つのオカリナにてアンサンブルを奏でるわけなので) かなり大変だったようですが、それでもブナの木のある森に優しく響く素朴な音色は、午前中一杯、竹の伐採作業に没頭して少々ハイになっていた僕らの心と体を癒して見事にクーリングダウンさせてくれました。
(これらの写真は、リハーサル風景を捉えたものです。午前の作業を終えて休憩場所に戻ってきたときに慌ててパチリ。リラックスされていて実に良い雰囲気でした。ちなみに僕を竹切りに誘い、この山と麓の集落の人々との関わりについて話をするように促して下さったのは、三人のうち向かって左の位置に立っていらっしゃっている方です。)
今回彼女たちの演奏を聴いて、そう思いました。
あらためて、拍手を送ります。
素敵な音色を聴かせていただきどうもありがとうございます。
野外でアコースティック楽器を上手に演奏しようとすること自体、かなりハイレヴェルな腕前を必要とすると言うのに、今回は初冬の冷え込む山頂での演奏。
気温や湿度など、空間のコンディションに大きく左右されるオカリナという楽器の (素材からもたらされる) 特性上、音程を安定させるのが (それも三人の持つ三つのオカリナにてアンサンブルを奏でるわけなので) かなり大変だったようですが、それでもブナの木のある森に優しく響く素朴な音色は、午前中一杯、竹の伐採作業に没頭して少々ハイになっていた僕らの心と体を癒して見事にクーリングダウンさせてくれました。
(これらの写真は、リハーサル風景を捉えたものです。午前の作業を終えて休憩場所に戻ってきたときに慌ててパチリ。リラックスされていて実に良い雰囲気でした。ちなみに僕を竹切りに誘い、この山と麓の集落の人々との関わりについて話をするように促して下さったのは、三人のうち向かって左の位置に立っていらっしゃっている方です。)

僕は彼女たちの演奏を聴いて、最近ずっと頭の中でプランを練り続けている山里センチメンツのミーティングがいつか実現したら、彼女たちをゲストとしてお招きしたいと思いました。
オカリナの音色は山里センチメンツという集まりが持つであろうムード、テイストにぴったりかもしれないな、と感じたからです。
(本件はまだまだ先の話になりそうなのですが、山里センチメンツ・ミーティングのロケーションのアイデアだけはまとまりつつあります。ただしまだ僕一人で勝手に考えている段階で、先方や僕の周りの人にはまだ何ら相談しておりません。もう少々、お待ちください。)
さて、実はこのブログを読んでくださっている方々宛てに、おかり~な・フレンズからメッセージを戴きましたのでぜひ目を通してくださいませ。
おかり~な・フレンズのみなさま、どうもありがとうございます。
*メッセージはこちら。↓
『豊田藤岡地区のオカリナ重奏グループ おかり~な・フレンズです。
メンバーは女性3人に男性1人のアマチュア組と プロの女性ピアニストを含めた5人組です。
主に豊田・藤岡・名古屋・静岡・岐阜などで演奏しています。
4人全員がすべて違うパート・楽器で演奏するスタイルをとっていて うまくいくときは綺麗なハーモニー しかしうまくいかないときは 何かぐちゃぐちゃになってしまうという爆弾の様な危険な音楽遊びにはまってしまった中年4人組です。
駒山当日は なんとアカペラの曲だけで 練習も約3回という恐ろしい事に挑戦してしまい やはり土ツボに見事はまってしまいました。すみません。
でも三回目にしての初めての清々しい天気・美しい紅葉・駒山の神様?仏様の見守り 参加者様の優しい拍手のおかげで何とか8曲 楽しく演奏させて頂きました。ありがとうございました。
次回は出来ましたら メンバー1の歴女のたっての希望もあり ヒストリーに纏わる曲をやりたいと思ってます。このブログの主さんとの歴史コラボになったらいいなということでしょうか?
出来はどうなるかまったくわかりませんが これから頑張って練習していきたいと思います。
現在 来年度の演奏会のスケジュール調整中です。
希望がありましたら お気軽に連絡してくださいませ。 おかり~な・フレンズ』
オカリナの音色は山里センチメンツという集まりが持つであろうムード、テイストにぴったりかもしれないな、と感じたからです。
(本件はまだまだ先の話になりそうなのですが、山里センチメンツ・ミーティングのロケーションのアイデアだけはまとまりつつあります。ただしまだ僕一人で勝手に考えている段階で、先方や僕の周りの人にはまだ何ら相談しておりません。もう少々、お待ちください。)
さて、実はこのブログを読んでくださっている方々宛てに、おかり~な・フレンズからメッセージを戴きましたのでぜひ目を通してくださいませ。
おかり~な・フレンズのみなさま、どうもありがとうございます。
*メッセージはこちら。↓
『豊田藤岡地区のオカリナ重奏グループ おかり~な・フレンズです。
メンバーは女性3人に男性1人のアマチュア組と プロの女性ピアニストを含めた5人組です。
主に豊田・藤岡・名古屋・静岡・岐阜などで演奏しています。
4人全員がすべて違うパート・楽器で演奏するスタイルをとっていて うまくいくときは綺麗なハーモニー しかしうまくいかないときは 何かぐちゃぐちゃになってしまうという爆弾の様な危険な音楽遊びにはまってしまった中年4人組です。
駒山当日は なんとアカペラの曲だけで 練習も約3回という恐ろしい事に挑戦してしまい やはり土ツボに見事はまってしまいました。すみません。
でも三回目にしての初めての清々しい天気・美しい紅葉・駒山の神様?仏様の見守り 参加者様の優しい拍手のおかげで何とか8曲 楽しく演奏させて頂きました。ありがとうございました。
次回は出来ましたら メンバー1の歴女のたっての希望もあり ヒストリーに纏わる曲をやりたいと思ってます。このブログの主さんとの歴史コラボになったらいいなということでしょうか?
出来はどうなるかまったくわかりませんが これから頑張って練習していきたいと思います。
現在 来年度の演奏会のスケジュール調整中です。
希望がありましたら お気軽に連絡してくださいませ。 おかり~な・フレンズ』
2012年12月05日
お礼とお詫びとお知らせ
稲武のまちを訪れた際にある本をたまたま手にとったことがきっかけで、素晴らしい人々と出会って有意義な時間を過ごすことができた、ということを記事にしました。
その本は稲武の歴史について詳しく知ることが出来るとても素晴らしい内容の本なのですが、その中の数ページを割いて、ある山のことが書いてありました。
その山とは。
何と先月の下旬に僕らが竹を切りに行った山だったのです。
その本は稲武の歴史について詳しく知ることが出来るとても素晴らしい内容の本なのですが、その中の数ページを割いて、ある山のことが書いてありました。
その山とは。
何と先月の下旬に僕らが竹を切りに行った山だったのです。
ブナの木を守るため三年前から竹の伐採を行っていらっしゃる方々に僕は今回初めて合流したのですが、人柄が良い方ばかりで、まごまごしている僕にとても親切にしてくださいました。
また、そもそもは北岡先生の森林学校を通じてたまたま集まったみなさんということで、つながりとしては割と緩やかな感じがしたのですが、コミニュケーションをはかるのがどなたも上手で、そしてとてもスマートな立ち振る舞いをされるので、僕は何のストレスも感じずに一緒に作業に没頭したり、会話を楽しむことができました。
人間が練られているひとたちとの触れあいは得るものが実に多くて、思い切って参加してみて本当に良かったと思いました。
また、そもそもは北岡先生の森林学校を通じてたまたま集まったみなさんということで、つながりとしては割と緩やかな感じがしたのですが、コミニュケーションをはかるのがどなたも上手で、そしてとてもスマートな立ち振る舞いをされるので、僕は何のストレスも感じずに一緒に作業に没頭したり、会話を楽しむことができました。
人間が練られているひとたちとの触れあいは得るものが実に多くて、思い切って参加してみて本当に良かったと思いました。
僕を竹切り作業に導いて下さった方について。
その方とは矢作川の源流を探るというテーマで森を歩く北岡先生の講座でご一緒しました。
講座の三回目のとき、別れ際に竹切りの日程や集合場所について尋ねたいと思って話しかけたら、
「竹切り作業の合間に山について何か話してみませんか、作業は大変疲れるものなので、休憩のときなどに地元の方から何か話が聞ければ皆の励みになると思うのです」
とおっしゃっていただいたのです。
この一言は僕にとってすごく嬉しいものでありましたが、同時にとても重い言葉でもありました。
生半可な話はできないな、そう思いました。
その気持ちを抱えて、山の麓のお寺の門を叩いたり、昔を知る伯母宅に押しかけて話を聞いたりしたのです。
竹切りの合間に何か話せ、と言って下さったから、あの山のことについて関わる多くの人たちから話を聞くことになり、その結果、僕が産まれる前の時代のあの山と麓の集落の関わりついて貴重な情報を得ることができたのでした。
その方とは矢作川の源流を探るというテーマで森を歩く北岡先生の講座でご一緒しました。
講座の三回目のとき、別れ際に竹切りの日程や集合場所について尋ねたいと思って話しかけたら、
「竹切り作業の合間に山について何か話してみませんか、作業は大変疲れるものなので、休憩のときなどに地元の方から何か話が聞ければ皆の励みになると思うのです」
とおっしゃっていただいたのです。
この一言は僕にとってすごく嬉しいものでありましたが、同時にとても重い言葉でもありました。
生半可な話はできないな、そう思いました。
その気持ちを抱えて、山の麓のお寺の門を叩いたり、昔を知る伯母宅に押しかけて話を聞いたりしたのです。
竹切りの合間に何か話せ、と言って下さったから、あの山のことについて関わる多くの人たちから話を聞くことになり、その結果、僕が産まれる前の時代のあの山と麓の集落の関わりついて貴重な情報を得ることができたのでした。
竹切り作業の当日。
お昼休みにお時間を頂戴し二十数名の方々を前に山と人々との関わりについての話をさせていただきました。
後で何人かの方から、良かったよ、とおっしゃっていただけて安心したのですが、とりとめがないと言うか、まとまりが悪いと言うか、とにかく聞きづらくて不細工な話しぶりであったのは間違いなくて、それでも何とかなったのは、聞いて下さった皆さんがあの山に興味を持っていらっしゃる方ばかりで、そしてみなさんお優しいので積極的に耳を傾けるようにしてくださったからに違いないと思うのでした。
お昼休みにお時間を頂戴し二十数名の方々を前に山と人々との関わりについての話をさせていただきました。
後で何人かの方から、良かったよ、とおっしゃっていただけて安心したのですが、とりとめがないと言うか、まとまりが悪いと言うか、とにかく聞きづらくて不細工な話しぶりであったのは間違いなくて、それでも何とかなったのは、聞いて下さった皆さんがあの山に興味を持っていらっしゃる方ばかりで、そしてみなさんお優しいので積極的に耳を傾けるようにしてくださったからに違いないと思うのでした。
そんな皆さんに、僕がおわびすべきことがいくつかあります。
まずは、準備を失敗し、あの日持っていくはずだった資料のいくつかを持っていけなかったこと。
その中には、麓のお寺の先代のご住職の若かりし頃のお写真などもありました。
「山のお寺のお坊さんと麓のお寺のお坊さん。気力に溢れる二人の若いお坊さんが檀家に向かうため山道を颯爽と歩く姿を想像してください。」
僕はみなさんに確かそんなようなことを言いましたが、あのときにご住職の写真をお見せできれば、もっともっとぐっとイメージが広がったのになと思うと悔しいです。
次に、写真や資料のコピーを地面にばらまいて置いたこと。みなさんに見ていただきやすいようにとやむを得ず思い切ってそうしたのですが、行儀の良いことではありませんでした。
ピンなどを持参していれば、手荷物などを置いていたあずまやの壁に貼ることができたなと、今さらながら思っております。
内容がまとまっておらず話しぶりも下手でかなり耳障りだったに違いないのに加えて、話が長くなってしまったこともお詫び申し上げます。
もしかしたら竹切りをする時間に少々くいこんでしまったかもしれません。すみませんでした。
とにかく寒い中、文句も言わずに話を聞いて下さりありがとうございます。
そして。
ちょっと不思議な話をいくつかしてしまったこと。
いまは少し後悔しています。
話さないようにしようと一度は心に決めていたのですが、つい話してしまいました。
中には、何だよその話は、と思われた方もいらっしゃったかも。
記憶違い、思いすごし、妄想、想像、その他諸々。
そういうものかもしれません。
どうかお許しください。
まずは、準備を失敗し、あの日持っていくはずだった資料のいくつかを持っていけなかったこと。
その中には、麓のお寺の先代のご住職の若かりし頃のお写真などもありました。
「山のお寺のお坊さんと麓のお寺のお坊さん。気力に溢れる二人の若いお坊さんが檀家に向かうため山道を颯爽と歩く姿を想像してください。」
僕はみなさんに確かそんなようなことを言いましたが、あのときにご住職の写真をお見せできれば、もっともっとぐっとイメージが広がったのになと思うと悔しいです。
次に、写真や資料のコピーを地面にばらまいて置いたこと。みなさんに見ていただきやすいようにとやむを得ず思い切ってそうしたのですが、行儀の良いことではありませんでした。
ピンなどを持参していれば、手荷物などを置いていたあずまやの壁に貼ることができたなと、今さらながら思っております。
内容がまとまっておらず話しぶりも下手でかなり耳障りだったに違いないのに加えて、話が長くなってしまったこともお詫び申し上げます。
もしかしたら竹切りをする時間に少々くいこんでしまったかもしれません。すみませんでした。
とにかく寒い中、文句も言わずに話を聞いて下さりありがとうございます。
そして。
ちょっと不思議な話をいくつかしてしまったこと。
いまは少し後悔しています。
話さないようにしようと一度は心に決めていたのですが、つい話してしまいました。
中には、何だよその話は、と思われた方もいらっしゃったかも。
記憶違い、思いすごし、妄想、想像、その他諸々。
そういうものかもしれません。
どうかお許しください。
では最後に次回の記事の予告を。
同じくお昼の休み時間に、気温が低い中で一所懸命オカリナを演奏して下さりあの山の空気をとても穏やかにしてくださったみなさんのことを書こうと思っています。
ちなみに僕を山に誘ってくださった方はその一員です。
どうぞお楽しみに。
同じくお昼の休み時間に、気温が低い中で一所懸命オカリナを演奏して下さりあの山の空気をとても穏やかにしてくださったみなさんのことを書こうと思っています。
ちなみに僕を山に誘ってくださった方はその一員です。
どうぞお楽しみに。
2012年12月05日
Roger Nichols

深夜に音楽を。
この曲について、何か解説するのは野暮というものでしょう。
(記事のタイトルに使える文字数に限りがありますので、アーティスト名をはしょりました。正確には、Roger Nichols & The Small Circle of Friends です。)
この曲について、何か解説するのは野暮というものでしょう。
(記事のタイトルに使える文字数に限りがありますので、アーティスト名をはしょりました。正確には、Roger Nichols & The Small Circle of Friends です。)
2012年12月04日
永とくやのいなかまんじゅう
稲武のまちなかにあるニコ天の奥さまから教えていただいたおまんじゅうがこれ。
懐かしい感じのする白くて小さな紙袋にいれてもらいました。
懐かしい感じのする白くて小さな紙袋にいれてもらいました。
帰宅して。
夕食をとってしばらくしてから奥さんがお茶を淹れてくれたので、早速いなかまんじゅうが入った白い袋をリヴィングのテーブルの上に置きました。
「あっ、何だか良いね、この袋。」
奥さんも僕と同じことを思ったようです。
「それにこれ、このおまんじゅうは手作りなんだ。作った人から手渡してもらったよ」
つぶあんが透けてみえます。
「形は少々いびつだったりするけれど、これはおばあちゃまの手のかたちなんだからいいんだ」
僕はそんなことを言いながら、おまんじゅうをパクリ。
永とくやのおばあちゃまお手製のおまんじゅうは、素朴な味わいながらも甘味と塩気のバランスが絶妙でした。
ニコ天の奥さまがファンだとおっしゃる理由が、よーくわかりました。
夕食をとってしばらくしてから奥さんがお茶を淹れてくれたので、早速いなかまんじゅうが入った白い袋をリヴィングのテーブルの上に置きました。
「あっ、何だか良いね、この袋。」
奥さんも僕と同じことを思ったようです。
「それにこれ、このおまんじゅうは手作りなんだ。作った人から手渡してもらったよ」
つぶあんが透けてみえます。
「形は少々いびつだったりするけれど、これはおばあちゃまの手のかたちなんだからいいんだ」
僕はそんなことを言いながら、おまんじゅうをパクリ。
永とくやのおばあちゃまお手製のおまんじゅうは、素朴な味わいながらも甘味と塩気のバランスが絶妙でした。
ニコ天の奥さまがファンだとおっしゃる理由が、よーくわかりました。
2012年12月04日
2012年12月03日
ニコ天は祖父が通ったお店なのです
ニコ天。
ここは今はなき祖父が、よく通っていたというお店。
僕の実家から稲武のまちなかまでの距離はたぶん10km強はあろうかと思うのですが、祖父は相当歳をとってからも愛車のホンダ・カブにまたがり、足繁く通ったそうです。
こちらでは鰻と天ぷらをいただくことができます。
祖父はこちらの天ぷらうどんが好きでよく食べていたと記憶。
稲武のまちでゆっくりする機会があったら必ず寄ろうと思っていた場所のひとつでしたが、今回ここで食事をとることができました。
僕の実家から稲武のまちなかまでの距離はたぶん10km強はあろうかと思うのですが、祖父は相当歳をとってからも愛車のホンダ・カブにまたがり、足繁く通ったそうです。
こちらでは鰻と天ぷらをいただくことができます。
祖父はこちらの天ぷらうどんが好きでよく食べていたと記憶。
稲武のまちでゆっくりする機会があったら必ず寄ろうと思っていた場所のひとつでしたが、今回ここで食事をとることができました。
下の火鉢とストーヴの写真で充分想像いただけると思いますが、とてもリラックスできるお店です。
稲武を経由するドライヴの道中に、落ち着いてお食事をとりたいと思われる方は、ぜひどうぞ。
稲武を経由するドライヴの道中に、落ち着いてお食事をとりたいと思われる方は、ぜひどうぞ。
この記事は、ひとつ前の記事からのつづきです。
この日の僕はタイヤを冬仕様のものに交換するために、実家からほど近い稲武のまちを訪れました。
(わが家はマンションなので、僕と奥さんの車のタイヤ計8本を置いておくスペースなど無いため、各々の実家の倉庫に置いているのです。)
交換作業をしてくださったモータースの事務所にて作業が終わるのを待っているとき、テーブルの上に置かれていた一冊の本が目にとまりました。
それは大変興味深いものだったのですが、残念ながら今から入手するのは困難な様子。
この日の僕はタイヤを冬仕様のものに交換するために、実家からほど近い稲武のまちを訪れました。
(わが家はマンションなので、僕と奥さんの車のタイヤ計8本を置いておくスペースなど無いため、各々の実家の倉庫に置いているのです。)
交換作業をしてくださったモータースの事務所にて作業が終わるのを待っているとき、テーブルの上に置かれていた一冊の本が目にとまりました。
それは大変興味深いものだったのですが、残念ながら今から入手するのは困難な様子。
それならばせめて同じ著者の方が書かれた別の本を探そう、と、このまちの本屋さんに向かった僕。
その本屋さんは僕が幼い頃、本好きの母に連れられてよく訪れたお店で、毎月発行される小学館の学年誌などを買ってもらったものでした。
お店の方は幼い僕の記憶に残っていた方でした。
「歴史がお好きなんですか」
そう声をかけていただけたのも、僕がお店の入口にほど近い本棚にあったこの本をしげしげと眺めていたから。
その本屋さんは僕が幼い頃、本好きの母に連れられてよく訪れたお店で、毎月発行される小学館の学年誌などを買ってもらったものでした。
お店の方は幼い僕の記憶に残っていた方でした。
「歴史がお好きなんですか」
そう声をかけていただけたのも、僕がお店の入口にほど近い本棚にあったこの本をしげしげと眺めていたから。
本屋の方とはそれから数十分、山あいの集落での暮らしや人々のことなど、様々な話をいたしました。
とても楽しい時間はあっという間に過ぎるもので、お昼を食べるのも忘れて話しこんでしまったのですが、お腹の方はちゃんと時を刻んでおりましたので、同じ著者の方が書かれた「語り継ぎたい稲武の歴史」というタイトルのこの本を買い求めてお店を後にしました。
(もしもこのブログを読んでくださっていたら・・・僕の長い話におつきあいいただき、ありがとうございました。)
その後。
僕は迷うことなくニコ天へ。
もう世間で言うお昼の時間を過ぎてしまっていたので恐る恐る暖簾をくぐると、遅いお食事をとられていたお店の方がさっと席を立って、いらっしゃいませ、どうぞ、どうぞ、と笑顔で店内に案内してくださいました。
僕はストーヴの近くの席に座り手早く食事をとったのち、さきほどの本屋さんで買い求めた本を、テーブルの上に広げました。
ゆっくり本を読んでいても嫌な顔をされそうもない雰囲気だったからです。
とても楽しい時間はあっという間に過ぎるもので、お昼を食べるのも忘れて話しこんでしまったのですが、お腹の方はちゃんと時を刻んでおりましたので、同じ著者の方が書かれた「語り継ぎたい稲武の歴史」というタイトルのこの本を買い求めてお店を後にしました。
(もしもこのブログを読んでくださっていたら・・・僕の長い話におつきあいいただき、ありがとうございました。)
その後。
僕は迷うことなくニコ天へ。
もう世間で言うお昼の時間を過ぎてしまっていたので恐る恐る暖簾をくぐると、遅いお食事をとられていたお店の方がさっと席を立って、いらっしゃいませ、どうぞ、どうぞ、と笑顔で店内に案内してくださいました。
僕はストーヴの近くの席に座り手早く食事をとったのち、さきほどの本屋さんで買い求めた本を、テーブルの上に広げました。
ゆっくり本を読んでいても嫌な顔をされそうもない雰囲気だったからです。
この本から、また会話が広がりました。
モータースで見かけたあの本がこちらのお店にも置いてあったからです。
そして何と「返すのはいつでも良いから、持っていってください。半年でも一年でも。」と貸していただけたのです。
(モータースでも社長が同じことを言って下さったのですが、そのときは恐縮して遠慮してしまったのでした。二度目なので、ありがたくお借りしました。)
ニコ天のお店の方とも数十分の間、様々なことを話しこんでしまいました。
僕がどうして地元にUターンしたのかとか、どうして高原で働くようになったのとか、奥さんとのなれそめとか、そういう話にも興味を持って聞いて下さいました。
さらにお店の方から、「私はこの人の書くものが好きなのよ。講演会にも行くぐらい。」と一冊の本の話をうかがいました。
それがこちら。
ニコ天の奥さまへ。
翌日、早速購入して読んでみました。
良い本を教えていただきどうもありがとうございます。
それと報告がもうひとつ。
教えていただいたおまんじゅう、帰りに買い求めました。
そのことは次回の記事に書くことといたします。
モータースで見かけたあの本がこちらのお店にも置いてあったからです。
そして何と「返すのはいつでも良いから、持っていってください。半年でも一年でも。」と貸していただけたのです。
(モータースでも社長が同じことを言って下さったのですが、そのときは恐縮して遠慮してしまったのでした。二度目なので、ありがたくお借りしました。)
ニコ天のお店の方とも数十分の間、様々なことを話しこんでしまいました。
僕がどうして地元にUターンしたのかとか、どうして高原で働くようになったのとか、奥さんとのなれそめとか、そういう話にも興味を持って聞いて下さいました。
さらにお店の方から、「私はこの人の書くものが好きなのよ。講演会にも行くぐらい。」と一冊の本の話をうかがいました。
それがこちら。
ニコ天の奥さまへ。
翌日、早速購入して読んでみました。
良い本を教えていただきどうもありがとうございます。
それと報告がもうひとつ。
教えていただいたおまんじゅう、帰りに買い求めました。
そのことは次回の記事に書くことといたします。
タグ :ニコ天語り継ぎたい稲武の歴史
2012年12月03日
2012年12月01日
目で見る稲武の歴史と文化
竹伐採をした日の話はここでちょっとお休みして、記事のタイトルとは無縁に思われる画像から、今回の話は始まるのです。
早いものでもう12月。
師走となりました。
高原に車で通う僕はここ最近
「そろそろ冬タイヤに変えねば。さて、いつ変えようか」
とタイミングを計っていたのですが、高原の近くに住む人がおととい
「三回目の氷が張ったよ」
とぼそりとつぶやいたので、決意をしました。
師走となりました。
高原に車で通う僕はここ最近
「そろそろ冬タイヤに変えねば。さて、いつ変えようか」
とタイミングを計っていたのですが、高原の近くに住む人がおととい
「三回目の氷が張ったよ」
とぼそりとつぶやいたので、決意をしました。
自身で交換することもできるのですが、バランスはやはりプロによる調整に任せたいと思い、お願いしました。
今回車を持ち込んだのは、僕の実家の近くにあるモータース。
先月、某お店にて一人で食事をした際にたまたまこちらの社長さんと席が隣になり、短い時間ではありましたがいろいろなお話をさせていただいたご縁があったのです。
今回車を持ち込んだのは、僕の実家の近くにあるモータース。
先月、某お店にて一人で食事をした際にたまたまこちらの社長さんと席が隣になり、短い時間ではありましたがいろいろなお話をさせていただいたご縁があったのです。
手早く交換作業が行われるなか、僕は社長さんに促されて事務所のソファへ。
座ってすぐに、テーブルの上に置いてあった一冊の本に目を奪われました。
座ってすぐに、テーブルの上に置いてあった一冊の本に目を奪われました。
本のタイトルは、「目で見る稲武の歴史と文化」。
以前から稲武という地は、聡明で博識な人を多く輩出しているという印象を持っていたのですが、この本はまさにそういう方の手によるもので、何と個人で執筆、出版されたものでありました。
すごいなぁと感心しながらページをどんどんめくっていく僕。
すると・・・
!
・・・そうです。
ここはつい先日、竹の伐採作業をした場所。
伐採作業に参加させていただくにあたり麓の地域の出身者として、山の上にあるこの古いお寺の歴史についてある程度の知識をつけて臨めた、と思っていた僕でしたが、この本を読んで、まだまだ知らないことが膨大にある、ということを再認識しました。
ううーん、と唸りながら本を読む僕。
不思議そうな顔をするモータースの社長さん。
意を決して、実はこの本について自身のブログの記事でちょっと触れたいんです、と僕が話すと、モータースの社長さんは何と著者の方にその場で電話をしてくださいました!
本の在庫はまだお持ちですか
もう人に渡せるものはないのですか、ではあるとしたらどこにありますか
このまちの本屋さんにもたぶん在庫がないということですか
矢継ぎ早に質問をする社長。
電話を通じて快く質問に答えてくださる著者の方。
あまりにもスピィーディーな展開にただただ唖然とする僕。
まあ、とにかく。
この電話がきっかけとなり、このまちに住んでいらっしゃるとても魅力的なひとたちとこの日の僕は次々と出会っていくことになるのでした。
To be continued.
・・・そうです。
ここはつい先日、竹の伐採作業をした場所。
伐採作業に参加させていただくにあたり麓の地域の出身者として、山の上にあるこの古いお寺の歴史についてある程度の知識をつけて臨めた、と思っていた僕でしたが、この本を読んで、まだまだ知らないことが膨大にある、ということを再認識しました。
ううーん、と唸りながら本を読む僕。
不思議そうな顔をするモータースの社長さん。
意を決して、実はこの本について自身のブログの記事でちょっと触れたいんです、と僕が話すと、モータースの社長さんは何と著者の方にその場で電話をしてくださいました!
本の在庫はまだお持ちですか
もう人に渡せるものはないのですか、ではあるとしたらどこにありますか
このまちの本屋さんにもたぶん在庫がないということですか
矢継ぎ早に質問をする社長。
電話を通じて快く質問に答えてくださる著者の方。
あまりにもスピィーディーな展開にただただ唖然とする僕。
まあ、とにかく。
この電話がきっかけとなり、このまちに住んでいらっしゃるとても魅力的なひとたちとこの日の僕は次々と出会っていくことになるのでした。
To be continued.
2012年11月30日
石焼き芋を食べて思ったことは
説明なんて不要ですよね。
しかしそれでも何か書け、と言われれば、ただ一言。
寒空の下で食べる石焼き芋は、とーっても、美味しかった
そう、書きます。
しかしそれでも何か書け、と言われれば、ただ一言。
寒空の下で食べる石焼き芋は、とーっても、美味しかった
そう、書きます。
焼き芋と言えば・・・この季節になると壺焼き芋の製法を研究することに日々熱中する僕なのですが、今回こうしてホームメイド&アウトドア風のをいただいてみて、石焼き芋の石焼き製法の良さを再確認することができました。
はい、そうです。
何事もこしらえかた次第、なのでした。
はい、そうです。
何事もこしらえかた次第、なのでした。
2012年11月29日
2012年11月26日
森でいただく豚汁は#2
写真を眺めていたら、あのときの美味しさを思い出してお腹が空いてきました。
ということで、具だくさん豚汁の写真を再び掲載。
この季節の森の中でいただく温かい豚汁は最高のご馳走でした。
前の前の記事にてちらりと触れましたが、この日の僕らは森の中にてひたすら竹を伐採して片づける作業を行いました。
(具だくさん豚汁はお昼ごはんのときに振る舞われたもの。持参のおにぎりは食べる頃には外気で冷たくなっていたので、ありがたかったです。)
僕の実家にほど近いところにある山の山頂にこの地域では珍しい木が二本だけ生えているのですが、人の手が入らなくなって久しいため周りが竹に覆われて鬱蒼としてしまったのです。
木の周りに陽が射すようにするため、三年前から有志の面々が立ちあがりボランティア活動にて竹を処理していらっしゃるのですが、縁あって僕も今回から一員に加わることになりました。
なかなか大変な作業である
結構重労働である
インターネット経由で過去の作業レポートを拝見したり、過去に参加した方から経験談を少々聞いて、それなりに覚悟をしていったのですが・・・想像以上の過酷さでありました!
しかしみなさん、本当に、本当によく働くのです。むしろそのことの方に驚きました。
ということで、具だくさん豚汁の写真を再び掲載。
この季節の森の中でいただく温かい豚汁は最高のご馳走でした。
前の前の記事にてちらりと触れましたが、この日の僕らは森の中にてひたすら竹を伐採して片づける作業を行いました。
(具だくさん豚汁はお昼ごはんのときに振る舞われたもの。持参のおにぎりは食べる頃には外気で冷たくなっていたので、ありがたかったです。)
僕の実家にほど近いところにある山の山頂にこの地域では珍しい木が二本だけ生えているのですが、人の手が入らなくなって久しいため周りが竹に覆われて鬱蒼としてしまったのです。
木の周りに陽が射すようにするため、三年前から有志の面々が立ちあがりボランティア活動にて竹を処理していらっしゃるのですが、縁あって僕も今回から一員に加わることになりました。
なかなか大変な作業である
結構重労働である
インターネット経由で過去の作業レポートを拝見したり、過去に参加した方から経験談を少々聞いて、それなりに覚悟をしていったのですが・・・想像以上の過酷さでありました!
しかしみなさん、本当に、本当によく働くのです。むしろそのことの方に驚きました。

縁あって、と書きましたがどんな縁なのかと言うと、そもそもは恥ずかしがり屋の僕(!)が意を決して森を歩く講座に参加したことに始まります。
三回あった講座のうちの初回が今回登った山だったのですが、ご一緒した方から
「あら、このあたりのご出身の方ですか。それは、それは。あっ、そうそう、わたしたちの中の何人かは11月に竹を切りに再びここに登りますよ。」
と教えていただいたのです。
このとき僕はとても驚きました。
なぜなら、たまたま去年、インターネットでその様子を拝見していたからです。
「ああ、この方たちがそうなのか・・・」
口には出しませんでしたが、幸運な出会いに感謝した次第です。
森を歩く講座にどうして参加したのかについては以前の記事で書きましたので、こちらとこちらをご覧下さい。
山育ちなのに木々や植物のことをまったく知らないし、草刈機なんて去年まで触ったことも無かった有様なので、職場では「ほんとにおぼっちゃまだねぇ」と何だか頭にくる例えにてからかわれておりますが、まあそんなことはできるだけ気にせずに、次回参加するであろう講座までに地味に愚直にお勉強を重ねる日々なのでした。
三回あった講座のうちの初回が今回登った山だったのですが、ご一緒した方から
「あら、このあたりのご出身の方ですか。それは、それは。あっ、そうそう、わたしたちの中の何人かは11月に竹を切りに再びここに登りますよ。」
と教えていただいたのです。
このとき僕はとても驚きました。
なぜなら、たまたま去年、インターネットでその様子を拝見していたからです。
「ああ、この方たちがそうなのか・・・」
口には出しませんでしたが、幸運な出会いに感謝した次第です。
森を歩く講座にどうして参加したのかについては以前の記事で書きましたので、こちらとこちらをご覧下さい。
山育ちなのに木々や植物のことをまったく知らないし、草刈機なんて去年まで触ったことも無かった有様なので、職場では「ほんとにおぼっちゃまだねぇ」と何だか頭にくる例えにてからかわれておりますが、まあそんなことはできるだけ気にせずに、次回参加するであろう講座までに地味に愚直にお勉強を重ねる日々なのでした。

森を歩く講座にエントリーした理由について書いた記事には書きませんでしたが、 Nordic Walking を始めるきっかけとなった三年前の北欧旅行は、今思えば僕の野山への興味、感心を喚起させるものでした。
特にフィンランドは、森と寄りそって、森に抱かれて暮らしている人々がたくさんいる国である、という印象を強く持ちあこがれの国となったのです。
帰国してすぐは (すっかりあちらの国々に魅了されてしまった僕だったので) 日本と北欧の国々の有様のあまりの違いに目まいを覚えるほどで、以前にましてますます自身の実家近くの野山になど魅力を何ら感じなくなったのですが、それでも時間経過とともに少しずつ、手が届く距離になかなか豊かな自然があるじゃないか、と気づき始めました。
そしてもうひとつ。
昨年の3月11日から続くあの出来事。
僕はあの件についてこのブログにおいては枝葉のことや知り合いのことしか書いておりませんが、あれは僕らの価値観を変える出来事でした。
我々は長く生きれば生きるほど、生と死の意味を考え続けることになります。
しかし僕の場合は、たとえば身近な人が亡くなったときとか、何かわかりやすいきっかけがあって宗教・信仰とは何かについてふと考えたりしたときとか、そういうタイミングでしか自分はどう生きるべきか、ということについて今まで深く考えたりしてこなかったのですが、情けないことにこの歳になって、そしてあんな出来事を知るに至って、そこでようやくいろいろなことに気づき始めたのでした。
気づきの結果が、思いきった転職であり、Nordic Walking Movement の活動であり、北岡先生とともに森を歩く講座への参加や不思議な縁がつづく今回のボランティア活動への参加、三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会への参加、そして Nordic Walking Movement に続きこれから自ら立ちあげる山里センチメンツのプロジェクトなのでした。
「あっ、何だか総括っぽいぞ、まとめてるぞ、いよいよこのブログも最終回か!?」
そう思われた方。
ハズレです。
まだまだ続きます。
今回のボランティア活動をアテンドしてくださった方宛てにメールを送ったところ、早速返信していただきまして (おっちょこちょいの僕が、竹伐採に使用した枝切り鋏を解散場所まで乗せてもらったその方の車のトランクの中に置き忘れたことから始まったメールやりとりなのでした!) このブログを読んでくださる旨や今回参加した方々や関係者の方々にこのブログのURLをシェアして下さる旨などが書かれていたのです。
そんなわけで、初めてご覧になる方向けに今回はこんな感じで文中に過去の記事へのリンクを多用する形としてみました。
ちなみに今年の夏の時点でも似たような記事を書いております。このときもたぶん誰かが新たに読んで下さることになりこんな体裁で書いたのだと記憶しております。
(ここまで読まれて「何だかごちゃごちゃして変なブログだな、よくわからないな」 と思われた方へ。Q&Aと題した記事をいくつか書いておりますのでぜひご参照くださいませ。)
次回の記事では、今回の竹切りの様子をもう少しだけ書きます。
作業は大変だったけれど、ぜひまた参加したい!と思えたのは、参加者のみなさんのお人柄がとても素晴らしかったから。
そのあたりの話を中心に、駄文で大変恐縮ですがせっせせっせと書きたいと思っています。
お楽しみに。
あ、それと参加された方々にいくつかお詫びしなければならないこともありました。
それも含めて、書きます。
To be continued.
特にフィンランドは、森と寄りそって、森に抱かれて暮らしている人々がたくさんいる国である、という印象を強く持ちあこがれの国となったのです。
帰国してすぐは (すっかりあちらの国々に魅了されてしまった僕だったので) 日本と北欧の国々の有様のあまりの違いに目まいを覚えるほどで、以前にましてますます自身の実家近くの野山になど魅力を何ら感じなくなったのですが、それでも時間経過とともに少しずつ、手が届く距離になかなか豊かな自然があるじゃないか、と気づき始めました。
そしてもうひとつ。
昨年の3月11日から続くあの出来事。
僕はあの件についてこのブログにおいては枝葉のことや知り合いのことしか書いておりませんが、あれは僕らの価値観を変える出来事でした。
我々は長く生きれば生きるほど、生と死の意味を考え続けることになります。
しかし僕の場合は、たとえば身近な人が亡くなったときとか、何かわかりやすいきっかけがあって宗教・信仰とは何かについてふと考えたりしたときとか、そういうタイミングでしか自分はどう生きるべきか、ということについて今まで深く考えたりしてこなかったのですが、情けないことにこの歳になって、そしてあんな出来事を知るに至って、そこでようやくいろいろなことに気づき始めたのでした。
気づきの結果が、思いきった転職であり、Nordic Walking Movement の活動であり、北岡先生とともに森を歩く講座への参加や不思議な縁がつづく今回のボランティア活動への参加、三河中山間地域で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会への参加、そして Nordic Walking Movement に続きこれから自ら立ちあげる山里センチメンツのプロジェクトなのでした。
「あっ、何だか総括っぽいぞ、まとめてるぞ、いよいよこのブログも最終回か!?」
そう思われた方。
ハズレです。
まだまだ続きます。
今回のボランティア活動をアテンドしてくださった方宛てにメールを送ったところ、早速返信していただきまして (おっちょこちょいの僕が、竹伐採に使用した枝切り鋏を解散場所まで乗せてもらったその方の車のトランクの中に置き忘れたことから始まったメールやりとりなのでした!) このブログを読んでくださる旨や今回参加した方々や関係者の方々にこのブログのURLをシェアして下さる旨などが書かれていたのです。
そんなわけで、初めてご覧になる方向けに今回はこんな感じで文中に過去の記事へのリンクを多用する形としてみました。
ちなみに今年の夏の時点でも似たような記事を書いております。このときもたぶん誰かが新たに読んで下さることになりこんな体裁で書いたのだと記憶しております。
(ここまで読まれて「何だかごちゃごちゃして変なブログだな、よくわからないな」 と思われた方へ。Q&Aと題した記事をいくつか書いておりますのでぜひご参照くださいませ。)
次回の記事では、今回の竹切りの様子をもう少しだけ書きます。
作業は大変だったけれど、ぜひまた参加したい!と思えたのは、参加者のみなさんのお人柄がとても素晴らしかったから。
そのあたりの話を中心に、駄文で大変恐縮ですがせっせせっせと書きたいと思っています。
お楽しみに。
あ、それと参加された方々にいくつかお詫びしなければならないこともありました。
それも含めて、書きます。
To be continued.
2012年11月26日
暮らしのヒント集 (暮らしの手帖社)

入院して治療をされている人に。
自宅で療養をされている方に。
退屈な時間を紛らわすための本を差し入れるとしたら。
僕ならば、この本を持参します。
たまたま開いたページから読み始められるし、簡潔な文章ばかりなので絵を眺めるように読めてさして疲れません。
それでも続けて読めば、眠れない人の眠気を誘うぐらいのことはしてくれるかもしれないし、取り組むのがとても難しい事柄は書かれてないので落ち込んでいる方が読まれれば、元気になったらあんなことをしよう、こんなことをしようという気持ちが沸き起こるかもしれません。
ふにゃふにゃ、もごもごした言い方ではなく、ぴしっ、と書かれているけれど、決して説教くさくないのも良いのです。
優しくてくだけた言い回しで、なんとかだもの、などとラフな筆づかいで書かれた標語のようなものもホッとできて良いのかもしれませんが、きれいな印刷書体を用いてこれぐらいカチっと書かれている文章の方が、僕は好きです。
自宅で療養をされている方に。
退屈な時間を紛らわすための本を差し入れるとしたら。
僕ならば、この本を持参します。
たまたま開いたページから読み始められるし、簡潔な文章ばかりなので絵を眺めるように読めてさして疲れません。
それでも続けて読めば、眠れない人の眠気を誘うぐらいのことはしてくれるかもしれないし、取り組むのがとても難しい事柄は書かれてないので落ち込んでいる方が読まれれば、元気になったらあんなことをしよう、こんなことをしようという気持ちが沸き起こるかもしれません。
ふにゃふにゃ、もごもごした言い方ではなく、ぴしっ、と書かれているけれど、決して説教くさくないのも良いのです。
優しくてくだけた言い回しで、なんとかだもの、などとラフな筆づかいで書かれた標語のようなものもホッとできて良いのかもしれませんが、きれいな印刷書体を用いてこれぐらいカチっと書かれている文章の方が、僕は好きです。
2012年11月25日
森でいただく豚汁は
最高でした!


2012年11月24日
2012年11月22日
2012年11月22日
茶室 助庵にて
こちらは初めて伺いましたが、ゆったりと落ち着ける場所でした。
誰かをご案内されるなら、ここで一服すると良いかも。
数日前までは対岸の銀杏が美しかったそうですから、来年は葉が落ちる前に訪れたいと思いました。
誰かをご案内されるなら、ここで一服すると良いかも。
数日前までは対岸の銀杏が美しかったそうですから、来年は葉が落ちる前に訪れたいと思いました。