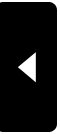2012年10月01日
山頂おにぎり
「山頂でおにぎり」、というタイトルにしようと思ってキーを叩いたら、ついうっかり「の」を抜かしてしまいました。
付け足そうと思いましたが、この響きも悪くないなと思い、そのままにしてみた次第。
付け足そうと思いましたが、この響きも悪くないなと思い、そのままにしてみた次第。
ここは大川入山の山頂。
そう前回の記事からのつづきなのですが・・・登山経過を記すのをはしょってしまいました。
そう前回の記事からのつづきなのですが・・・登山経過を記すのをはしょってしまいました。
この日はとても良いお天気で、山頂からの眺めは素晴らしく
高低差約800メートルを一気に駆け登ってきた僕らにとって
ご褒美のような景色でした。
中央に広がるのは飯田の街なみ。
そしてその向こうには
そしてその向こうには
八ケ岳連峰や
乗鞍岳や穂高岳・・・
名だたる山々を一度に望むことができました。
(実物ではなく案内版の写真で、そしてそれもうまく写っていない写真で大変恐縮です。実際の山々は、ぜひ大川入山の山頂からごらんください。)
To be continued.
タグ :大川入山
2012年09月29日
登山口はあららぎ高原 -大川入山-
雲ひとつない、秋晴れのある日。
先日に続いて再び、森を歩く講座に参加しました。
森、と言っても今回はれっきとした山登り。
なにせ1,908メートルの山頂を徒歩にて目指すのですから。
なにせ1,908メートルの山頂を徒歩にて目指すのですから。
スノーモービルやスキーリフトを横目に登り始めて間もなく。
「これはトウヒです。」
講師の先生がそう言いながら手渡して下さいました。
トウヒという単語を聞いて、心は一気にアラスカへ。
僕が尊敬する写真家の星野道夫氏の著作にたびたび登場する針葉樹なのです。
この日の登山口はあららぎ高原スキー場でした。
既にこの時点で標高は1,145メートルですから、なかなか高いところからのスタート。
しかし。
ここから800メートル近くを登らねば山頂には着けないのでした。
遊歩道
なんてお気楽に書いてありますが・・・。
なんてお気楽に書いてありますが・・・。
To be continued.
2012年09月21日
森のえびフライ レシピ
森に落ちていた"えびフライ"のことを以前の記事に書きましたが、その正体について書くのをすっかり忘れていました。
(と上から目線で偉そうに書きましたけど、僕も森林学校の講座に参加するまではこのえびフライのことなど知りもしなかったのです。)
(と上から目線で偉そうに書きましたけど、僕も森林学校の講座に参加するまではこのえびフライのことなど知りもしなかったのです。)
2012年09月20日
山頂にて
山頂にて。
以前の記事でお弁当を広げていたのはここです。
(山の名前と標高が書かれた小さな木の看板が置かれていました。看板には今年の二月中旬の日付が!置いてくださった方々は、とても寒い季節に登られたのですね!)
(山の名前と標高が書かれた小さな木の看板が置かれていました。看板には今年の二月中旬の日付が!置いてくださった方々は、とても寒い季節に登られたのですね!)
竹林で覆われていたせいで長らく光が入らず暗くうっそうとしていたという山頂は・・・
今ではかなり切り開かれ太陽の光が一面に射していました。
三年ぐらい前から有志のみなさんらで随分手を入れられてきたのだそうです。
(そのことをつい最近知ったのも、実は今回の森歩きに参加しようと思った理由のひとつでした。)
三年ぐらい前から有志のみなさんらで随分手を入れられてきたのだそうです。
(そのことをつい最近知ったのも、実は今回の森歩きに参加しようと思った理由のひとつでした。)
年に二回ほど山に登り、この山頂の竹を伐採されているとのこと。
もちろん切るだけではありません。切った竹をそのままそこに置いておくわけにはいきませんから。
もちろん切るだけではありません。切った竹をそのままそこに置いておくわけにはいきませんから。
よいしょ、よいしょと運んで、せっせ、せっせと並べて・・・切ったあとの後始末もかなりの重労働のはずです。
パソコンの画面越しではなく、実際に山頂に立って見てみて、作業に従事されたみなさまの頑張りに頭が下がるばかり。
パソコンの画面越しではなく、実際に山頂に立って見てみて、作業に従事されたみなさまの頑張りに頭が下がるばかり。
講師の先生や過去にボランティアにて伐採活動に参加された方によれば、決して竹や竹林が悪いわけではなくて、あくまでもこの山の場合は、山頂の植生を整えるために竹にどうしても犠牲になってもらわざるを得ないとのことでした。
様々なことを考えてみた結果、このブログに今回訪ねた森がある山の名前を記すことはやめました。
(とはいえ、上に山の名前が書かれた看板の画像を掲載したので、山の名前を含めたいくつかのキーワードでインターネット検索すれば、みなさんはこの山に関する多くの情報を得ることができるわけですが。)
(とはいえ、上に山の名前が書かれた看板の画像を掲載したので、山の名前を含めたいくつかのキーワードでインターネット検索すれば、みなさんはこの山に関する多くの情報を得ることができるわけですが。)
山のふもとにほど近いところに実家があるというだけで、そしてたった一度、伐採後の山に登ったというだけで、多くを書けるものではありません。
僕がいますべきことは、この山と森について薄っぺらいことをペラペラしゃべったりスラスラ書いたりすることではなくて、まずは愚直に足を運ぶことなのだな、と今回の体験を通じて思いました。
僕がいますべきことは、この山と森について薄っぺらいことをペラペラしゃべったりスラスラ書いたりすることではなくて、まずは愚直に足を運ぶことなのだな、と今回の体験を通じて思いました。
ただし。
人知れず地道に、終わりがないかと思われるようなハードワークを山中で一所懸命して下さっている方々が、それも無償で汗をかいてくださっている方々がたくさんいらっしゃるということは、ここにしっかり書いておかなければいけないと思います。
山が寂れ、お寺が朽ちていることを記したいくつかのインターネット上の文章の中で、ふざけた人たちを山に呼び込んでしまいかねない配慮が不足した迂闊な記事を見かけました。
木々や草花を痛めつけ、ゴミを捨て、そしてさらなる倒壊の危険があるお寺の中に肝試しのつもりで立ち入る人々。
そういう人たちを誘いかねない記事。
問題ある文言の削除や訂正をぜひしていただきたいものです。
それともうひとつ。
父母に聞いた話ですが、今は亡き僕の祖母がまだ元気だった頃は祖父母らを含めたふもとの集落の人々がこの山に定期的に登って、山門やお寺の掃除や手入れなどをしたり、花をたむけたりお供えをしていたそうです。
そういう時代が確かにあったということも、ここに書いておかねばなりません。
山の恩恵を受けて暮していた人々が確かにいた。
人々は感謝の気持ちを持って頻繁に山に登り森を歩いていた。
山歩きをする人ならば、そういう光景に思いを馳せずして、寂れた、朽ちた、果てた、などと簡単に言い捨てるのは良くないなと思うのです。

この山のふともの集落はダム建設の影響によって一気に過疎化が進み、その後日本各地の山あいの集落がたどるのと同じような経緯で高齢化がどんどん進みました。
山の手入れがなされなかったのも、お寺が崩れてしまったのも、上に書いたこととは無縁ではないと思われますが、その理由のすべてを紐解くのは今となっては容易なことではありません。
日本のあちこちで、お寺や神社の立て直しが大変困難な状況になっているようです。
この山のように、既に人がいないお寺はもちろんのこと、人がいるお寺でも苦しいのですから。
それに未来に向かってその状況はますます悪化するに違いなく、なす術もなく朽ちていくケースを我々は目の当たりにするばかりでしょう。
人知れず地道に、終わりがないかと思われるようなハードワークを山中で一所懸命して下さっている方々が、それも無償で汗をかいてくださっている方々がたくさんいらっしゃるということは、ここにしっかり書いておかなければいけないと思います。
山が寂れ、お寺が朽ちていることを記したいくつかのインターネット上の文章の中で、ふざけた人たちを山に呼び込んでしまいかねない配慮が不足した迂闊な記事を見かけました。
木々や草花を痛めつけ、ゴミを捨て、そしてさらなる倒壊の危険があるお寺の中に肝試しのつもりで立ち入る人々。
そういう人たちを誘いかねない記事。
問題ある文言の削除や訂正をぜひしていただきたいものです。
それともうひとつ。
父母に聞いた話ですが、今は亡き僕の祖母がまだ元気だった頃は祖父母らを含めたふもとの集落の人々がこの山に定期的に登って、山門やお寺の掃除や手入れなどをしたり、花をたむけたりお供えをしていたそうです。
そういう時代が確かにあったということも、ここに書いておかねばなりません。
山の恩恵を受けて暮していた人々が確かにいた。
人々は感謝の気持ちを持って頻繁に山に登り森を歩いていた。
山歩きをする人ならば、そういう光景に思いを馳せずして、寂れた、朽ちた、果てた、などと簡単に言い捨てるのは良くないなと思うのです。
この山のふともの集落はダム建設の影響によって一気に過疎化が進み、その後日本各地の山あいの集落がたどるのと同じような経緯で高齢化がどんどん進みました。
山の手入れがなされなかったのも、お寺が崩れてしまったのも、上に書いたこととは無縁ではないと思われますが、その理由のすべてを紐解くのは今となっては容易なことではありません。
日本のあちこちで、お寺や神社の立て直しが大変困難な状況になっているようです。
この山のように、既に人がいないお寺はもちろんのこと、人がいるお寺でも苦しいのですから。
それに未来に向かってその状況はますます悪化するに違いなく、なす術もなく朽ちていくケースを我々は目の当たりにするばかりでしょう。
今後は、山の手入れのお手伝いをしつつ、お寺についても地道にコツコツと、自身に出来る限りのことをしたいと思っています。
(まずは11月に行われるという本年二回目の竹伐採作業に運搬・清掃要員として参加します!参加予定のみなさま、どうぞよろしくお願い申し上げます!)

(まずは11月に行われるという本年二回目の竹伐採作業に運搬・清掃要員として参加します!参加予定のみなさま、どうぞよろしくお願い申し上げます!)
2012年09月20日
千匹大絵馬があった場所
先日の森歩きのとき、久々にここに訪れることができました。
なにせ前回訪れたのは僕が小学生の頃でしたから。
ただいま勉強中です。
どうにかしたいんですけど、どうにかするにはどうしたら良いのかわからないので、勉強しているのです。
なにせ前回訪れたのは僕が小学生の頃でしたから。
ただいま勉強中です。
どうにかしたいんですけど、どうにかするにはどうしたら良いのかわからないので、勉強しているのです。
2012年09月18日
森を歩く講座にエントリーしたわけ #2
前回の記事からの続きです。
山里育ちなのに山を知らない・・・。
しかし何ら気にならなかったのです、数年前までは。
短い期間に両親が立て続けに手術を受けたある時期とか。
昨年の震災の後とか。
それまでとは違う感覚が僕の中で芽生えました。
なぜかやけに、木々や草花の緑が眩しいな、愛おしいな、と思うようになったのです。
それは、誰の人生もやはりたった一度きりで、それはいつか必ず終わりが来るのだな、と、ごくごく当たり前のことを実感したから、かもしれません。
そう、人間だけではありませんね。命あるもの、すべて、です。
すべては一度きり。
始まりは終わり。
終わりは始まり。
しかし何ら気にならなかったのです、数年前までは。
短い期間に両親が立て続けに手術を受けたある時期とか。
昨年の震災の後とか。
それまでとは違う感覚が僕の中で芽生えました。
なぜかやけに、木々や草花の緑が眩しいな、愛おしいな、と思うようになったのです。
それは、誰の人生もやはりたった一度きりで、それはいつか必ず終わりが来るのだな、と、ごくごく当たり前のことを実感したから、かもしれません。
そう、人間だけではありませんね。命あるもの、すべて、です。
すべては一度きり。
始まりは終わり。
終わりは始まり。

今から木々や草花の名前を覚えるのは正直ちょっとめんどうなのですが、めんどうだけど始めてみようかな、と思い始めたとき、たまたま森を歩く講座のことを知り、おまけにその行き先のひとつが僕の地元からほど近い場所だったものですから、これはエントリーしろってことだな、と思ったのです。
2012年09月17日
森を歩く講座にエントリーしたわけ #1
森を歩く講座にエントリーした理由。
それを書きます。
僕の祖父は山で仕事をしていた人でした。
と言っても、猟師や木こりだったわけではなくて、木材を得るための山々を地主さんと交渉を重ねて買い取る担当だったそう。つまり、一応会社員だったわけです。
しかしそんな業務を担当する部署を抱える会社なんて、今の日本ではどれほどあるのでしょうか。
昔に比べて山の価値が小さくなったと言われる現代。僕の実家でも山を持っていますが、その価値はあってないようなもののようです。扱いやすさの面で建築資材により適した安い輸入材の台頭や木を用いた住宅の建築需要が少なくなったことで国産の木材を扱う商売が衰退したからです。
しかし戦後しばらくは価値がかなり高かったそう。
その昔。
僕らの国では木材を大量に必要とした時代があり、天然林を伐採した場所に成長が速くて木材加工に適したスギやヒノキなどを植えてせっせせっせと人工林を作ったのでした。
人々を後押ししたのは、国。
国の政策だったのです。
スギやヒノキを植えた山は宝の山。
皆、そう思いました。
そしてもちろん、実際に儲けた人も大勢いたそうです。
あっ、いけない。
話がとても大きくなってしまいました。
とにかく、祖父が山に関係した仕事をしていたのです。
そして僕はと言えば、産まれた場所は市内のキユーピー工場のそばでしたが、二歳頃には祖父のいる家(父の実家)に転居
して、山と川に囲まれた山里で大きくなるまで暮らしました。
しかし、何というか、うちの祖父は孫である僕に山のことをあまり教えようとはしませんでした。
あまり、というよりまったく、と言っても良いかもしれません。
家の縁側に行けば目の前に見えるというのに。
祖父のスタンスは僕の父に対してもほぼ同じ。もちろん父の場合は、父が幼い頃はそうでもなかったようですが、いつの頃からか、「これからの時代は山などを持っていてももう仕方がない」、祖父はそう思ったようです。
ですから父も祖父と同様に僕に山のことを教えることはいままでほとんどなく、結果、僕は山のことなど何も知らないまま、人生を生きてきたのです。とはいえ、教えられなくても自然と自ら興味を抱くこどもだっているでしょうから、祖父や父のせいにばかりしていられませんが・・・僕の場合はそんな感じだったのです。
長くなってしまいました。
この続きは、次回の記事で。
2012年09月16日
噛むと甘いのです
森を歩いた話のつづきです。
講師の先生にすすめられて、葉の端を口に含んで噛んでみたところ、甘味を感じました。
嫌みのない良い甘味で、僕はその味をとても気に入りました。
引き続きガムを噛むように、噛みました。
むむ。美味。
嫌みのない良い甘味で、僕はその味をとても気に入りました。
引き続きガムを噛むように、噛みました。
むむ。美味。
味もさることながら、とても良い香りがするのです。
上品な良い香りで、しばしかいでいると何だかリラックスできそうな気がしました。
「昔の人は山仕事の合間にかじったそうです。この葉っぱ、疲れたときに良いと思いませんか、山歩きの最中にたまにかじると疲れた体が癒されます。」
というようなことを講師の先生が教えて下さいました。
上品な良い香りで、しばしかいでいると何だかリラックスできそうな気がしました。
「昔の人は山仕事の合間にかじったそうです。この葉っぱ、疲れたときに良いと思いませんか、山歩きの最中にたまにかじると疲れた体が癒されます。」
というようなことを講師の先生が教えて下さいました。
この植物はタムシバとかカムシバ、またはニオイコブシなどと呼ばれているそうです。
To be continued.
2012年09月15日
ブナの木を目指して
前回の記事からのつづきです。

森を歩いた、と書きましたが、この日僕らが目指したのは、ブナの木。
標高は1000mに満たないながらも、森や植物に詳しい専門家の先生が
「なかなか面白い森があります。」
とおっしゃる山を登ったのでした。
上の写真は、その山の山頂にあるブナの木のたもとに到達したところ。


標高は1000mに満たないながらも、森や植物に詳しい専門家の先生が
「なかなか面白い森があります。」
とおっしゃる山を登ったのでした。
上の写真は、その山の山頂にあるブナの木のたもとに到達したところ。
ブナの木に

触れてみました。

みな、思い思いの場所によっこらしょと腰をおろして、ブナの木を眺めながらランチをいただきました。
では、ここから少しずつ時計の針を戻してゆきたいと思います。

(To be continued.)
(To be continued.)
2012年09月13日
ブナの実など
今日は森を歩きました。
仕事で、ではなくて、プライヴェートで参加した森林学校の講座にて。
これらは僕が家に持ち帰ったもの。
奥さんへのお土産です。
仕事で、ではなくて、プライヴェートで参加した森林学校の講座にて。
これらは僕が家に持ち帰ったもの。
奥さんへのお土産です。

これらはブナの実。
殻はなかなか可愛い形をしています。
こちらは・・・おなじみのえびフライ
・・・ではなくて。さて、正体は何だと思いますか?
何回かに分けて、今回の森歩きを記事に綴ります。
お楽しみに。
・・・ではなくて。さて、正体は何だと思いますか?
何回かに分けて、今回の森歩きを記事に綴ります。
お楽しみに。
2012年08月12日
Entry
森を歩きます。
9月、10月、11月。
月に一回ずつ、合計三回。
近隣および近県の森を歩くとある催しに、メールにてエントリーしてみました。
参加希望者が定員人数を上回った場合は抽選とのこと。
エントリーに至った理由。
それはとてもここにサラサラと書けるような類のものでは、ないのです。
9月、10月、11月。
月に一回ずつ、合計三回。
近隣および近県の森を歩くとある催しに、メールにてエントリーしてみました。
参加希望者が定員人数を上回った場合は抽選とのこと。
エントリーに至った理由。
それはとてもここにサラサラと書けるような類のものでは、ないのです。

・・・なんて書くと、知りたくなるのが人情。
しかし、書けません。
書けないのです。
もし書いたとしても誰にも迷惑はかからないし、せいぜい僕が、ちょっとおかしな奴だ、と思われるぐらい。
むしろ記事としてはとても面白いものになるかもしれません。
それでも、書かない。
書かない方が良い気がしてならないからです。
理由はさておき、とにかく参加申し込みをしたことだけはこの記事にメモしておこう、という何だかよくわからないモヤモヤした心境にて、パソコンのキーをこうして叩いているのでした。
しかし、書けません。
書けないのです。
もし書いたとしても誰にも迷惑はかからないし、せいぜい僕が、ちょっとおかしな奴だ、と思われるぐらい。
むしろ記事としてはとても面白いものになるかもしれません。
それでも、書かない。
書かない方が良い気がしてならないからです。
理由はさておき、とにかく参加申し込みをしたことだけはこの記事にメモしておこう、という何だかよくわからないモヤモヤした心境にて、パソコンのキーをこうして叩いているのでした。